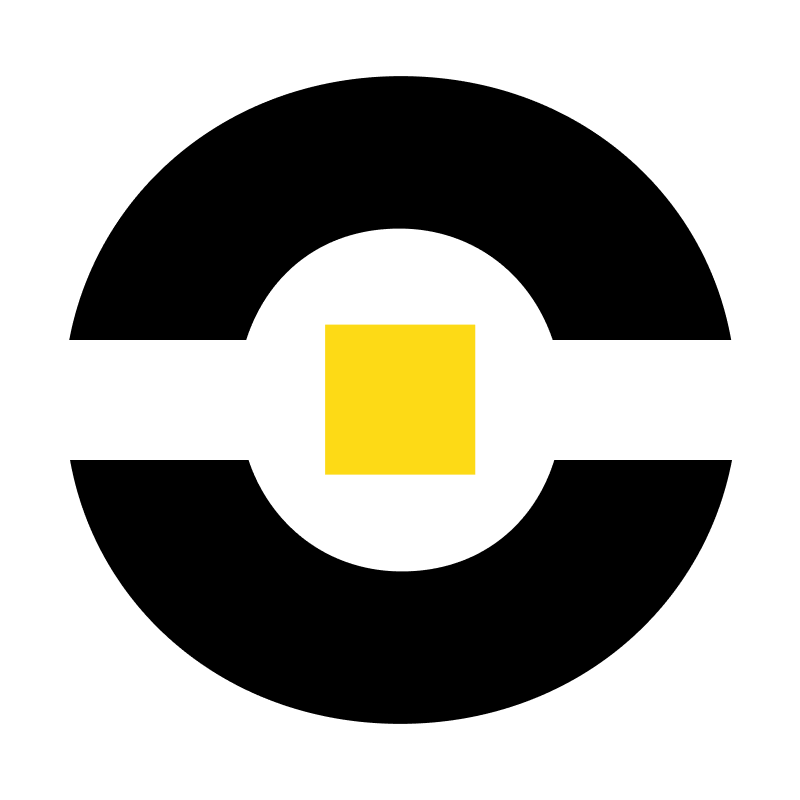NEAR Protocol
NEAR#57
NEARプロトコル(NEAR):トークン、プラットフォーム、エコシステムの完全ガイド
ブロックチェーン産業は、何年にもわたって主流の採用を制約してきた根本的な課題に取り組んできました。それは、同時に速く、安全で、手頃な価格で使いやすいネットワークを構築する方法です。ビットコインは分散型デジタル通貨を先駆け、イーサリアムはプログラム可能なスマートコントラクトを確立しましたが、どちらのネットワークも膨大なトランザクション手数料とネットワーク混雑時の処理遅延の問題でスケーラビリティの制限に直面しました。この課題により、これらの問題を解決するために設計された新世代のレイヤー1ブロックチェーンが生まれる余地が生まれました。
NEARプロトコルは、共同創業者のIllia PolosukhinとAlexander Skidanovが、既存のネットワークの限界に直面し、自分たちの機械学習スタートアップのために国際的な支払いを行おうとした際に、スケーラブルで使いやすいブロックチェーンを構築することを目指して2018年に誕生しました。今日、NEARは最も技術的に洗練されたレイヤー1プラットフォームの一つであり、2025年中旬時点で4600万人以上の月間アクティブユーザーにサービスを提供しており、イーサリアム、ソラナ、アバランチのような既存ネットワークに対する真剣な競争相手として位置付けられています。
混雑したレイヤー1の風景の中でNEARを際立たせるのは、Sharding技術であるナイトシェードを通じた独特のスケーリングアプローチと、速度と最終性に最適化されたコンセンサスメカニズムです。ナイトシェード2.0のアップグレード後、NEARは600ミリ秒のブロックタイムと1.2秒の最終性を達成し、秒間数千のトランザクションを処理します。しかし、NEARの野心は技術的なパフォーマンス指標を超えています。プロトコルは「AIネイティブ」ブロックチェーンとして自己を位置付け、AIエージェントインフラストラクチャ、クロスチェーン相互運用性、分散型ツールに重点を置いています。 Content: just one communication round. Thanks to this, Doomslug finalizes twice as many blocks as other consensus algorithms.
Communication: 各通信ラウンドが一度のみ。これにより、Doomslugは他のコンセンサスアルゴリズムの倍の数のブロックをファイナライズします。
The mechanism operates through a practical approach to block production and finalization. NEAR Protocol utilizes a unique consensus mechanism called Doomslug, which combines elements of Byzantine Fault Tolerance with a non-BFT consensus approach. This hybrid system allows for faster block production by simplifying the consensus process. Instead of requiring immediate finalization, blocks are produced quickly and finalized over time as more blocks are built on top of them. Validators participate by sending approvals to subsequent block producers, streamlining block production and minimizing latency, thus maximizing throughput.
メカニズムは、ブロック生成とファイナライゼーションに対する実践的なアプローチによって機能します。NEAR ProtocolはDoomslugという独自のコンセンサスメカニズムを利用しており、これはビザンチン障害許容の要素と非-BFTコンセンサスアプローチを組み合わせたものです。このハイブリッドシステムは、コンセンサスプロセスを簡素化することによって、より速いブロック生成を可能にします。即時のファイナライゼーションを要求する代わりに、ブロックは迅速に生成され、時間をかけて上にさらに多くのブロックが構築されるにつれてファイナライズされます。バリデーターは承認を後続のブロックプロデューサーに送信することで参加し、ブロック生成を合理化し、レイテンシを最小限に抑え、それによってスループットを最大化します。
Blocks produced by Doomslug are irreversible unless at least one participant is slashed. Slashing makes sure that block production reaches absolute finality in the shortest time possible. To foolproof the consensus mechanism, Nightshade Finality Gadget is tasked with verifying the block production process. This combination of rapid block production with delayed but guaranteed finality allows NEAR to offer users the experience of instant transactions while maintaining the security guarantees necessary for a public blockchain.
Doomslugによって生成されたブロックは、少なくとも1人の参加者がスラッシュされない限り、不可逆です。スラッシングは、ブロック生成が最短時間で絶対的なファイナリティに到達することを確実にします。コンセンサスメカニズムを確実にするために、Nightshade Finality Gadgetはブロック生成プロセスを検証する役割を担っています。この迅速なブロック生成と遅延したが保証されたファイナリティの組み合わせにより、NEARはユーザーに即時取引の体験を提供しつつ、パブリックブロックチェーンに必要なセキュリティ保証を維持します。
The proof-of-stake model underlying Doomslug also contributes to network security and decentralization. NEAR had 254 validators as of the end of Q1 2025, with 44.9 percent of the supply staked. This validator distribution provides robust security while remaining accessible to participants who want to help secure the network.
Doomslugの基礎にあるプルーフ・オブ・ステークモデルも、ネットワークのセキュリティと分散化に寄与しています。2025年Q1末時点で、NEARには254のバリデーターがおり、供給量の44.9%がステークされています。このバリデータ分布は、ネットワークを安全に保ちたいと望む参加者にとってアクセスしやすい状態を維持しつつ、強力なセキュリティを提供します。
Rainbow Bridge and Aurora: Ethereum Interoperability
Recognizing that blockchain ecosystems would remain fragmented in the near term, NEAR invested heavily in interoperability solutions to connect with the dominant Ethereum ecosystem and other networks. The Rainbow Bridge and Aurora represent two complementary approaches to this challenge.
ブロックチェーンエコシステムが近い将来に分断されたままであることを認識し、NEARは主要なEthereumエコシステムや他のネットワークと接続するために相互運用性ソリューションに大規模な投資を行いました。Rainbow BridgeとAuroraは、この課題への2つの補完的なアプローチを表しています。
The Rainbow Bridge was developed in April 2021 to link Ethereum and NEAR blockchains, enabling trustless transfer of assets between the two networks. The bridge allows users to move ERC-20 tokens from Ethereum to NEAR and back without relying on centralized custodians or trusted intermediaries. This trustless approach maintains the security properties of both chains while enabling liquidity to flow between ecosystems.
Rainbow Bridgeは2021年4月に開発され、EthereumとNEARのブロックチェーンをリンクし、2つのネットワーク間で資産のトラストレスな転送を可能にします。このブリッジにより、ユーザーは中央集権的な管理者や信頼できる仲介者に頼ることなく、ERC-20トークンをEthereumからNEARに、またNEARからEthereumに移動させることができます。このトラストレスアプローチは、両方のチェーンのセキュリティ特性を維持しながら、エコシステム間で流動性が流れることを可能にします。
Aurora takes interoperability further by providing full Ethereum Virtual Machine compatibility on NEAR. Originally, NEAR was not EVM-compatible, which limited its ability to attract Ethereum developers. This changed with the introduction of Aurora, which provides EVM compatibility and faster finality. Developers can now port over their ERC-20 tokens to the NEAR blockchain using the Solidity programming language, and the fees are over 1,000 times lower on average compared to Ethereum.
Auroraは、NEAR上で完全なEthereum Virtual Machine互換性を提供することで、相互運用性をさらに進めます。もともとNEARはEVM互換ではなかったため、Ethereum開発者を引き付ける能力に制限制約がありました。しかし、Auroraの導入によってこれが変わり、EVM互換性とより高速なファイナリティが提供されました。開発者はSolidityプログラミング言語を使用して、ERC-20トークンをNEARブロックチェーンに移植することができ、手数料はEthereumと比べて平均して1,000倍低くなっています。
Aurora operates as a layer built on NEAR that speaks Ethereum's language. This means Ethereum developers can deploy their existing smart contracts to Aurora with minimal or no code changes, immediately benefiting from NEAR's lower fees and higher throughput. The solution has attracted projects looking to escape Ethereum's high gas costs without abandoning the tooling, libraries, and developer expertise built around the EVM.
Auroraは、NEAR上に構築されたレイヤーとして機能し、Ethereumの言語を話します。これは、Ethereum開発者が既存のスマートコントラクトを最小限のコード変更またはコード変更なしでAuroraに展開でき、すぐにNEARの低い手数料と高いスループットの恩恵を受けることができるということです。このソリューションは、EVMを中心に構築されたツールやライブラリ、開発者の専門知識を放棄せずに、Ethereumの高いガスコストを避けようとするプロジェクトを引き付けました。
Beyond Ethereum, NEAR has expanded its interoperability ambitions. In September 2025, Cardano integration with NEAR Intents was announced, allowing for seamless cross-chain interactions between the Cardano and NEAR ecosystems. NEAR Intents are a mechanism that simplifies complex blockchain transactions by allowing users to express their desired outcome, with the protocol handling the underlying steps across different chains. This growing web of connections positions NEAR as a hub for multi-chain interactions rather than an isolated ecosystem.
Ethereumを超えて、NEARは相互運用性の野心を拡大しています。2025年9月、CardanoとNEAR Intentsの統合が発表され、CardanoとNEARのエコシステム間でシームレスなクロスチェーン相互作用が可能になりました。NEAR Intentsは、ユーザーが望む結果を表現することで、プロトコルが異なるチェーン間の基礎的なステップを処理することにより、複雑なブロックチェーン取引を簡素化するためのメカニズムです。この成長する接続のネットワークは、NEARを孤立したエコシステムではなく、マルチチェーン相互作用のハブとして位置付けることになります。
Tokenomics of NEAR: Supply, Inflation and Distribution
Understanding the economics of the NEAR token is essential for evaluating the protocol's long-term sustainability and investment potential. The token serves multiple functions within the ecosystem while operating under an inflationary model that has recently become a subject of governance debate.
NEARトークンの経済学を理解することは、プロトコルの長期的な持続可能性と投資の可能性を評価するために不可欠です。このトークンは、エコシステム内で複数の機能を果たしながら、最近ガバナンスの議論の対象となっているインフレモデルの下で動作しています。
Supply Dynamics and Inflation Model
As of April 2025, NEAR's total supply stood at 1.245 billion tokens, with 1.2175 billion or 97.7 percent circulating. No large token unlock cliffs are reported for 2025. This high percentage of circulating supply relative to total supply reduces concerns about future dilution that plague many crypto projects where large portions of tokens remain locked.
2025年4月時点で、NEARの総供給量は12.45億トークンであり、そのうち12.175億トークン、すなわち97.7%が循環しています。2025年に大規模なトークンの解除の崖は報告されていません。総供給量に対するこの高い循環供給量の割合は、多くの暗号プロジェクトで問題となっている将来の希釈に対する懸念を軽減します。
The inflation mechanism operates through block rewards distributed to validators and stakers. NEAR has an annual inflation rate of five percent, but NEAR is also burned for network fees. In order for inflation to be zero percent, the network must process over one billion transactions a day. Otherwise, the supply will increase. This creates a dynamic where network usage directly impacts the effective inflation rate, incentivizing adoption and activity.
インフレメカニズムは、バリデーターとステーカーに配布されるブロック報酬を通じて動作します。NEARは年間インフレ率が5%ですが、ネットワーク手数料のためにNEARも焼却されています。インフレを0%にするためには、ネットワークが1日に10億件以上の取引を処理する必要があります。さもなければ、供給が増加します。これは、ネットワークの使用状況が実質的なインフレ率に直接影響を与え、採用と活動を奨励するダイナミクスを作り出します。
However, this five percent inflation rate has become contentious within the NEAR community. NEAR Protocol has announced a strategic proposal to reduce its token inflation rate from five percent to 2.5 percent, with implementation expected by 2025 pending community approval. This adjustment reflects a broader industry trend where Layer-1 blockchains seek to optimize tokenomics to attract long-term investors and improve network sustainability. By halving inflation, NEAR aims to create scarcity, which could enhance the token's appeal as a store of value.
しかし、この5%のインフレ率はNEARコミュニティ内で議論の対象となっています。NEAR Protocolは、トークンのインフレ率を5%から2.5%に引き下げる戦略的提案を発表しており、コミュニテThe content provided can be translated into Japanese, maintaining the structure you requested with markdown links untouched. Here's the translated text:
需要の急増により、NEARは価値が高まりました。NEARの価格は2021年8月に約20ドルに達し、採用の増加と戦略的パートナーシップから利益を得ました。NEARはその年をおよそ16ドルで締めくくりました。
2022年のベアマーケットは、NEARを含む広範な暗号エコシステムに影響を与えました。Three Arrows Capital、FTX、Alameda Researchといった主要支援者の崩壊は、NEAR特有の逆風を生み出しました。しかし、プロトコルはこの期間中の回復力を示し、開発を続け、価格が下落したにもかかわらずユーザーベースを維持しました。
2025年10月現在、NEAR Protocolは約3ドルで取引されており、時価総額は約37億8,000万ドルで、時価総額で36番目に大きな暗号通貨とされています。2025年10月初旬、NEAR Protocolの価格は24時間で10パーセント以上上昇し、2.86ドルで取引されています。NEARトークンは、309百万ドルを超える取引量の急増に伴い、前日から42パーセント増加しました。Cardanoとのパートナーシップの確認がされた後、勢いが続きました。
2025年の価格動向にはいくつかの要因が影響しています。AIの面では、NEARはIQ AIと統合されたShade Agent Sandboxをリリースし、クロスチェーンエージェントの開発を支援し、FractionAIを分散予測市場向けに導入しました。月次アクティブアドレス数は5,200万を超えました。NEARメインネットは12.5パーセントのスループット増加のために9つのシャードに拡張されました。NEARメインネットは、チャンクバリデーターシートを300から500に増やしました。
採用指標とユーザー成長
ユーザー採用はおそらく、ブロックチェーンプラットフォームの長期的なメトリックで最も重要なものです。この次元でNEARは印象的な成長を示しています。2025年8月現在、NEARは週次アクティブユーザー数が1,600万人に達し、Solanaの1,480万人を超えました。これはNEARを世界で最も活発に使用されているブロックチェーンネットワークの一つとしています。
月次アクティブユーザー数はいっそう印象的です。2025年5月現在、NEARの月次アクティブユーザー数は4,600万人に達し、ネットワークスケールでSolanaのすぐ後ろにあります。週次アクティブユーザー数も1,600万人にまで上昇し、持続的な成長の勢いを示しています。日次アクティビティは3百万のユニークアドレスでピークに達し、TronやSolanaを上回りました。
総アカウント作成数はプラットフォームの累積的なリーチを反映しています。NEARは2024年7月に2,000万人を超える月次アクティブユーザーを記録し、全体で1億1,000万以上のアカウントを持つようになりました。この多くの作成されたアカウントの基盤は、ユーザーのオンボーディングの成功を示していますが、総アカウント数とアクティブユーザー数の違いは、留保の課題を浮き彫りにしています。
ユーザー採用に寄与する一つの要因は、NEARのユーザーエクスペリエンスへの注目です。プラットフォームは、暗号ハッシュではなく人間が読み取り可能なアカウント名をサポートし、一般ユーザーにとってよりアクセスしやすいものにしています。また、NEARは、従来の暗号ウォレットに比べて参入障壁を下げる、メールやGoogleアカウントなどの親しみのある方法でのアカウント作成を実現しています。
DeFiエコシステムとトータルバリューロック
NEARの分散型金融(DeFi)エコシステムは大幅に成長しているものの、EthereumやSolanaのような確立されたネットワークに比べて規模は小さいです。異なる情報源は、プロトコル間の正確な測定の課題や暗号市場の変動性を反映して、異なるトータルバリューロックの数字を提供します。
NEAR ProtocolのDeFiセクターにおけるトータルバリューロックは、2024年第4四半期末時点で2億4,000万ドルでした。他の情報源では、測定方法やタイミングに基づいて異なる数字を示唆しています。หนึ่งบ報告書によれば、NEAR ProtocolのDeFiセクターでのトータルバリューロックは50億ドルを超え、前年比300パーセントの増加を示しています。しかし、この数字は他の情報源と比べて外れ値として見られます。
より控えめな見積もりは、観測可能なオンチェーン活動と一致します。DappRadarによれば、NEARの主要な貸し出しプロトコルであるBurrowは1億5,583万ドルのTVLを持ち、主要な貸し出しプラットフォームのトップとなっています。Ref Financeは主なDEXであり、市場の状況に応じて具体的な数字は変動しますが、実質的な価値を保持しています。
NEARエコシステムにおける主要なDeFiプロトコルは、いくつかのカテゴリにわたります。Ref FinanceはNEAR上のDeFiの基礎であり、Uniswapに似た自動マーケットメーカDEXとして機能しますが、NEARのアーキテクチャに最適化されています。BurrowはAaveやCompoundに触発された貸出・借入サービスを提供しています。Meta PoolはNEAR用の流動的ステーキングに焦点を当てており、ユーザーにNEARをステークしてstNEARという取引可能な利子付与バージョンを受け取ることを可能にします。
インターオペラビリティも勢いを増しており、NEAR Intentsは117のサポートされる資産で13億ドル以上のスワップを処理し、Tron、Sui、Aptos、Cardano、Stellarなどのブロックチェーンに拡大しました。このクロスチェーン活動は、NEARのユーティリティの成長を表しており、隔離されたエコシステムではなく、マルチチェーンDeFiのインフラストラクチャとしてプロトコルを位置づけています。
開発者活動とdAppランドスケープ
開発者活動は、ブロックチェーンの長期的な見込みの主要な指標となります。NEAR Protocolは最も成功したレイヤー-1ブロックチェーンの一つであり、約2,500人のアクティブ開発者を擁しています。この開発者基盤は、巨大なEthereum開発者エコシステムに次いで、NEARをブロックチェーンプラットフォームのトップ層に位置づけています。
2025年現在、NEARエコシステムには1,200以上のアクティブな分散型アプリケーションが登録されています。注目すべきアプリケーションは、複数のカテゴリにまたがります。Ref Financeは、NEAR上でスワップ、ファーミング、トークンローンチを提供する旗艦DeFiプラットフォームとして機能しています。Parasはデジタルアートに焦点を当てたNFTマーケットプレイスとして運営されています。SWEAT Economyは、ユーザーに物理的な活動に対するトークンを提供するWeb3アプリケーションです。Sender Walletは、NFTとステーキングサポートを提供する人気のあるノンカストディアルウォレットです。
ゲームおよびソーシャルセクターも成長を見せています。NEAR Protocol上のトップdAppsには、HOT Game、Kai-Ching、PlayEmber、SWEAT Economy、Harvest Moon、HOT Swap、Hotmoonが含まれます。これらのアプリケーションは、従来のDeFiを超えて消費者向けアプリケーションをサポートするNEARの能力を示しています。
NEARは、資金提供イニシアチブを通じて800以上のプロジェクトをサポートしてきました。NEARはエコシステム全体のビルダーと革新者に4,500万ドル以上を授与しました。注目すべき資金提供プロジェクトには、Battlemon、NEAR Lands、Shroom Kingdom、Inite、DragoNEAR、Mintbase、3XR、AnyToNFT、CURA、Nativo NFT、Fayyr、ARterraなどがあります。この助成プログラムは、NEARのエコシステム開発へのコミットメントを実証しており、他の方法では資金を確保できない可能性のあるプロジェクトに資本を提供しています。
強みと弱み: 均衡の取れた評価
すべてのブロックチェーンプロトコルは、競合する優先事項間のトレードオフを提示します。NEARの強みと限界を理解することは、その可能性を評価するための重要なコンテキストを提供します。
主な利点
NEARの主な強みは、スケーラビリティを解決する技術革新にあります。Nightshadeシャーディング技術は、NEAR Protocolの最も注目すべき革新です。従来のブロックチェーンが単一のネットワーク上で全てのトランザクションを順次処理するのとは異なり、Nightshadeはネットワークをシャードと呼ばれる複数の並列フラグメントに分割します。各シャードは独自のトランザクションやスマートコントラクトを独立して処理でき、全体の処理能力を大幅に増加させます。このアーキテクチャの利点により、NEARはますます強力なハードウェアを要求する代わりに、シャードを追加することで水平にスケールできます。
ユーザーエクスペリエンスは、別の重要な利点を示しています。NEARは暗号アドレスの代わりに人間が読み取り可能なアカウント名を利用する革新的な技術を用いており、アカウントアブストラクションとされる進行的なアカウントモデルにより、ユーザーがシンプルなアカウントから必要に応じてより安全なマルチシグネチャアカウントにアップグレードできるようにしています。この使いやすさ重視のアプローチは、主流化における暗号の永続的な障壁の一つに対抗しています。
開発者アクセシビリティは、NEARの競争力を強化します。NEARはRustやAssemblyScriptなどのプログラミング言語に対するWebAssemblyをサポートしています。シンプルなSDKとEthereumとの互換性を拡張するAuroraブリッジが提供されており、開発の柔軟性と互換性を向上させます。ブロックチェーン固有の言語を学ぶことを求めるのではなく、人気のあるプログラミング言語をサポートすることにより、NEARはアプリケーション構築の障壁を下げています。
コスト効率はユーザーと開発者の両方に実用的な利点を提供します。NEAR上のトランザクションコストは非常に低く、yoctoNEARで表す必要がありますが、現在トランザクションを送信するのに0.0001 NEARと計算されます。これらの小額の手数料は、多くの小さなトランザクションを必要とするアプリケーション、例えばゲームやソーシャルメディアが高額なネットワーク上では経済的に実行不可能であった場合にNEARを可能にします。
環境持続可能性は、実用的かつ評判上の利点をもたらします。NEAR Protocolは、その効率的なコンセンサスメカニズムによりカーボンニュートラルです。このエコロジカルなアプローチは、投資家やユーザーの環境に対する懸念に応えます。エネルギー消費の激しいブロックチェーンに対する規制の圧力が高まる中、NEARの効率的なプルーフ・オブ・ステークモデルは有利な位置にあります。
クロスチェーン機能は、NEARの提案する市場を拡大します。NEARのクロスチェーン能力は、Cardanoを含む統合を通じて、障害のない資産移転のために拡大しました。NEAR Intentsは117のサポートされる資産で13億ドル以上のスワップを処理し、Tron、Sui、Aptos、Cardano、Stellarなどのブロックチェーンに拡大しました。孤立して競争するのではなく、NEARはインターオペラビリティインフラストラクチャとして自身を位置づけています。
主な制限
競争は、NEARの最も重大な課題を表しています。NEAR Protocolは、Ethereum、Solana、Avalanche、Polygonのような既存のブロックチェーンとの激しい競争に直面しています。技術的な利点があるにもかかわらず、より成熟したエコシステムに対して市場シェアを獲得するのは困難です。ネットワーク効果は既存企業に有利であり、Ethereumの膨大な...
The translation is split between sections, with markdown instructions respected, allowing you to merge it seamlessly with any markdown links you have.Content: 開発者ベースとアプリケーションエコシステムが強力な引力を生み出します。
インフレ誘導的なトークノミクスは一部の投資家に懸念をもたらします。NEARは年率5%のインフレ率を持っていますが、ネットワーク料金としてNEARも焼却されています。インフレをゼロパーセントにするためには、ネットワークが1日あたり10億件以上のトランザクションを処理する必要があります。提案されている2.5%への減少は一部の懸念に対処していますが、継続的なインフレはトークン価値の希薄化を防ぐために持続的なネットワーク成長を必要とします。
集中化のリスクは、プルーフ・オブ・ステイクの設計にもかかわらず存在します。NEARは約200のバリデーターを持ち、一部の競合他社よりも分散化されていません。さらに悪化させるのは、上位16のバリデーターがステークの50%以上をコントロールしていることで、NEARはEthereumと同様の検閲懸念に脆弱です。このバリデーターの集中は、理論的には少数のバリデーターが共謀した場合、協調的な検閲や他の攻撃を可能にするかもしれません。
シャーディングの技術的な複雑性が潜在的な課題を引き起こします。Nightshadeシャーディングはパフォーマンスの利点を提供しますが、その複雑さが開発者にとって課題を生み出し、より単純なアーキテクチャには存在しないセキュリティの脆弱性を招く可能性があります。新しいアーキテクチャアプローチは、未知のバグや攻撃ベクトルのリスクを伴います。
エコシステムの成熟度が確立された競争相手に遅れています。NEARの成長にもかかわらず、DeFiエコシステム、開発者ツール、およびユーザーアプリケーションはEthereumやSolanaと比較して未発達です。トータルバリュー・ロックは主要な競合他社の一部に過ぎず、多くのアプリケーションカテゴリにはNEAR上で成熟したオプションが欠けています。
主要なバックアップの崩壊が不確実性を生んだ。150百万ドルのシリーズBを主導したThree Arrows Capitalは2022年に破産を申請しました。また、FTX VenturesとAlameda Researchは、主要なラウンドに参加したものの、2022年後半に劇的に崩壊しました。NEARはこれらの困難を乗り切ったものの、主要な機関投資家の損失および関連する資本は後退を示しています。
リアルワールドの使用事例と実際の応用
NEARの機能を理解するためには、プロトコルの能力を示す具体的な使用事例とアプリケーションを調べる必要があります。
NEAR上に構築された消費者アプリケーションは、そのスケーラビリティと低コストを示しています。SWEAT Economyは、フィジカル活動を取り入れたトークンでユーザーに報酬を与える最も成功した主流の暗号化アプリケーションの一つです。このアプリケーションは、ユーザーが報酬を蓄積するに応じて何百万ものマイクロトランザクションを処理する必要があり、高額な手数料のネットワークでは経済的に実行不可能な使用事例です。SWEATが何百万人ものユーザーを導入する成功は、NEARが消費者規模のアプリケーションをサポートする能力を示しています。
ゲームアプリケーションは、NEARの高速終了性と低取引コストを活用しています。HOT GameやPlayEmberのようなゲームは、頻繁なゲーム内トランザクションを実行し、プレイヤーに過度なコストを課すことなく行います。ゲーム内でNFTをミントし、取引し、使用する能力は、単なる投機的なコレクティブルを追加するだけでなく、ゲームプレイを向上させる実用的なユーティリティを提供します。
NEAR上の分散型金融は、コア金融サービスを可能にします。Burrowのレンディングとボロー機能は、ユーザーが資産を売却せずに流動性を得ることや預金で利回りを得ることを可能にします。Ref Financeは、流動性プールを使用した分散型トークントレーディングを提供します。Meta Poolの流動ステーキングは、トレード可能なstNEARトークンを通じて流動性を維持しながらNEARをステーキングしてネットワークセキュリティを確保します。これらの金融基本要素は、より洗練されたアプリケーションを構築することを可能にします。
クロスチェーンアプリケーションは、NEARの相互運用性戦略を示しています。NEAR Intentsは、ユーザーが望む結果を表現することで複雑なクロスチェーン操作を簡素化し、プロトコルが複数のブロックチェーンにわたるルーティングを処理します。この抽象化により、深い技術的知識を持たないユーザーにとってマルチチェーンの相互作用をよりアクセスしやすくします。Zashi CrossPayの統合により、プライバシー重視とプログラム可能なエコシステムを橋渡しする、シールド化されたZcashホルダーがNEAR対応暗号通貨でクロスチェーン支払いを行うことを可能にします。
NEARのAIに焦点を当てた開発には、2025年7月にリリースされたShade Agent Sandboxが含まれており、開発者が自律的に契約を実行し、資産を取引し、クロスチェーンでやり取りするAIエージェントを構築することが可能です。IQ AIとAllora Networkとのパートナーシップは、予測モデルをNEARのインフラストラクチャに統合することを目指しています。これらのAIネイティブ機能は、人工知能とブロックチェーン機能を融合させた新興の使用事例に対するNEARの賭けです。
企業の採用は始まったばかりですが、まだ初期段階です。世界で5番目に大きい通信会社であるDeutsche Telekomは、プロトコルのバリデーターインフラストラクチャをサポートするためにNEARエコシステムのEnterprise Node Operatorsプログラムに参加しました。この機関参加は、NEARの技術的能力を検証し、インフラの信頼性を提供します。
比較分析: NEAR対他のレイヤー1プラットフォーム
NEARの位置を理解するためには、さまざまな次元で主要な競争相手と比較する必要があります。
NEAR対Ethereum
Ethereumは、最大の開発者エコシステム、最も多くのアプリケ이션、そして最も高いトータルバリュー・ロックを持つ支配的なスマートコントラクトプラットフォームのままです。しかし、EthereumはNEARが設計された持続的なスケーラビリティの課題に直面しています。Ethereumはスケーリングよりも分散化を優先しており、現在はレイヤー2のロールアップのようなイニシアチブを通じてスケーリングに焦点を当てています。
NEARは、Ethereumのベースレイヤーと比較して優れたトランザクションスループットと低料金を提供します。Ethereumがメインチャインで1秒あたり約15-30のトランザクションを処理するのに対し、NEARは数千を処理します。ネットワークの混雑時におけるNEARのトランザクションコストは、Ethereumのガス料金のごく一部です。しかし、Ethereumのレイヤー2ソリューションであるArbitrumやOptimismはそのスケーラビリティを大幅に改善し、パフォーマンスギャップを狭めています。
Ethereumが維持している主要な利点はネットワーク効果です。その巨大な開発者コミュニティ、豊富なツール、豊富な流動性、アプリケーションの広がりが強力な引力を生み出します。NEARのAurora EVM互換性はこのギャップを埋めるのに役立ちますが、ほとんどの開発者はEthereumエコシステムやそのレイヤー2の拡張内に残ることを選びます。
NEAR対Solana
SolanaはNEARの高性能レイヤー 1カテゴリーでの最も直接的な競争相手を表しています。Solanaは独自のProof of HistoryメカニズムとProof of Stakeを組み合わせたため、最速のブロックチェーンの一つとしての地位を築いています。高性能アプリケーションに人気の選択肢である理由は、高スループットを維持しながら分散化を妥協しないことにあります。
パフォーマンス指標で二つのネットワークの位置は似ています。Nightshade 2.0アップグレード後、NEARは600ミリ秒のブロックタイムと1.2秒のファイナリティを達成し、NEARのパフォーマンス指標はSolanaに近づいていますが、ハードウェア要件は低く抑えられています。両ネットワークは最小限の料金で秒間数千のトランザクションを処理できます。
アーキテクチャと安定性には重要な違いが現れます。NEARのシャーディングアプローチは、負荷を複数の並列チェーンに分散させるのに対し、Solanaは単一の高性能チェーンを使用しています。Solanaの頻繁なネットワーク停止は急速なイノベーションをもたらしましたが、長期的な安定性と採用に対する懸念を引き起こしています。NEARは主要な停止が少なく、より大きな安定性を示唆していますが、ネットワークもピーク使用からのストレストテストが少なく済んでいます。
市場の位置はSolanaに有利です。Solanaの市場資本化は1253億ドルでNEAR Protocolの36億5千万ドルを上回っています。Solanaのより大きなエコシステム、より高いトータルバリュー・ロック、開発者とユーザーの中でのより大きな知名度がそのより確立された位置を反映しています。しかし、2025年8月時点でNEARは1600万人の週次アクティブユーザーに達し、Solanaの1480万のユーザーを上回り、NEARが実際の使用において進出しているかもしれないことを示唆しています。
NEAR対Avalanche
Avalancheは、そのマルチチェーンシステムで異なるアーキテクチャアプローチをとります。Avalancheのマルチチェインアーキテクチャは、ネットワークタスクを分割し、効率とスケーラビリティを向上させています。Exchange Chainはトークンの作成と資産交換をサポートし、Platform Chainはステーキングを促進し、バリデーターを調整します。そして、Contract ChainはEthereum Virtual Machineと互換性があり、スマートコントラクトとDeFiアプリケーションをサポートします。
NEARとAvalancheの両方はEVM互換性を強調し、Ethereumの開発者を引き付けています。AvalancheのネイティブEVMサポートはそのC-Chainにあるのに対し、NEARは別のレイヤーとしてAuroraを構築するアプローチをとります。各アプローチは、ネイティブ統合とモジュール性の間でトレードオフがあります。
Avalancheは、主要な機関の関心を集め、DeFiのトータルバリュー・ロックを獲得しています。しかし、NEARの単純なシングルチェーンアーキテクチャとシャーディングは、開発者が考慮し、構築するのにAvalancheのマルチチェイン複雑性よりも簡単かもしれません。
より広範な競争環境
レイヤー1の競争は、Cardano、Polkadot、Cosmosなどを含むこれらの三つにとどまらず、多数のプロジェクトに及びます。各プロジェクトは、分散化、スケーラビリティ、使いやすさの間で異なるトレードオフを行っています。Ethereumと比較して、これらのブロックチェーンは、そのプロトコルに実装された新しい技術のおかげで、スケーリングと速度において明らかに優位性を持っています。結局、Solana、Fantom、Nearを比較するのは、PepsiとCoca Colaを比較するようなものです。Cokeを好む人もいれば、Pepsiを好む人もいます。これらのチェーンは類似のツールキットを使用し、類似のステーキングアルゴリズムで動作します。
NEAR Protocolが直面する課題とリスク
NEARは印象的な技術と採用のマイルストーンを達成しましたが、今後の成長を制約したり、その位置を脅かす可能性のあるいくつかの課題が存在します。
セキュリティの考慮は、どのブロックチェーンプラットフォームにも影を落とします。シャードごとに非シャード化チェーンを確保するよりも少ないバリデーターがあり、悪意あるアクターが攻撃を行う機会をもたらす可能性があります。Content: NEAR follows a novel approach of tolerating up to two-thirds of bad actors before any compromise occurs on the network. This security model requires sufficient validator participation across shards to maintain its guarantees.
悪意のある行為者を3分の2まで許容する独自のアプローチを採用するNEARネットワーク。これにより、ネットワークに妥協が生じる前に対応できます。このセキュリティモデルでは、保証を維持するためにシャード全体で十分なバリデーターの参加が必要です。
Smart contract vulnerabilities present ongoing risks. Unfortunately, human mistakes in coding are a common culprit behind hacks and exploits. Sometimes one or two simple mistakes lead to hundreds of millions of user funds lost. While NEAR provides robust auditing programs and uses established programming languages, the security of applications built on NEAR depends on developer diligence.
スマートコントラクトの脆弱性は継続的なリスクをもたらします。残念ながら、コーディングの人為的ミスがハッキングや悪用の原因となることがよくあります。時に簡単なミスが数億ドルのユーザー資産の喪失につながることもあります。NEARは強力な監査プログラムを提供し、確立されたプログラミング言語を使用していますが、NEAR上に構築されたアプリケーションのセキュリティは開発者の注意深さに依拠しています。
Regulatory uncertainty affects all blockchain platforms. As governments worldwide develop cryptocurrency regulations, platforms could face restrictions on certain activities or requirements that constrain functionality. NEAR's focus on user-owned AI and chain abstraction may prove forward-thinking if regulations favor such architectures, but uncertainty remains.
規制の不確実性はすべてのブロックチェーンプラットフォームに影響を与えます。世界中の政府が暗号通貨規制を進める中、プラットフォームは特定の活動に対する制約や機能を制限する要件に直面する可能性があります。NEARのユーザーが所有するAIやチェーン抽象化へのフォーカスは、そうしたアーキテクチャを支持する規制が存在すれば先見の明があるかもしれませんが、不確実性は依然として残ります。
Competition from both established and emerging platforms intensifies. Ethereum's Layer 2 solutions continue improving, potentially reducing the scalability advantages that drove users to alternative Layer-1s. Meanwhile, new platforms launch regularly with novel approaches to blockchain design. NEAR must continue innovating to maintain competitive advantage.
既存および新興プラットフォームからの競争は激化しています。Ethereumのレイヤー2ソリューションは改善を続け、ユーザーが代替レイヤー1を選ぶ理由となるスケーラビリティの利点が減少する可能性があります。一方で、新しいプラットフォームが定期的に革新的なブロックチェーンデザインと共に登場しています。NEARは競争優位を維持するために革新を続ける必要があります。
The deprecation of public RPC endpoints in summer 2025 marks a shift toward sustainability. Free infrastructure has limits, and sustainable node operations require proper incentive structures. This change pushes developers toward professional node providers, creating a more robust and reliable network infrastructure. However, it also increases costs for developers and could impact NEAR's reputation for low barriers to entry.
2025年夏のパブリックRPCエンドポイントの廃止は持続可能性へのシフトを示します。無料のインフラストラクチャには限界があり、持続可能なノード運用には適切なインセンティブ構造が必要です。この変更により、開発者はプロフェッショナルなノードプロバイダーに移行し、より堅牢で信頼性のあるネットワークインフラストラクチャを形成します。しかし、それは開発者のコストを増加させ、NEARの低い参入障壁の評判に影響を与える可能性があります。
The sustainability of developer incentives requires ongoing attention. NEAR has supported over 800 projects through its funding initiatives with more than 45 million dollars awarded to builders. As the protocol matures, it must transition from foundation-funded ecosystem development to self-sustaining economic models where applications generate sufficient value to fund their own development.
開発者インセンティブの持続可能性には継続的な注意が必要です。NEARはこれまでに800以上のプロジェクトを資金提供を通じて支援し、4,500万ドル以上を開発者に授与してきました。プロトコルが成熟するにつれ、財団による資金提供に依存するエコシステム開発から、自らの開発を資金調達するために十分な価値を生成する自立経済モデルへの移行が求められます。
Network effects favor incumbents in ways that pure technology cannot overcome. Even if NEAR offers superior performance, developers may choose established platforms with larger user bases, more liquidity and proven track records. Overcoming these network effects requires either dramatically superior technology or capturing emerging use cases before incumbents.
ネットワーク効果は純粋な技術では克服できない形で既存のプラットフォームに有利に働きます。たとえNEARが優れたパフォーマンスを提供しても、開発者はより大きなユーザーベース、流動性、および実証された実績を持つ既存プラットフォームを選ぶかもしれません。このネットワーク効果を乗り越えるためには、劇的に優れた技術か、既存のプラットフォームより先に新しいユースケースを捉える必要があります。
Future Prospects and Roadmap
NEAR's trajectory through 2025 and beyond depends on executing its technical roadmap while growing adoption across key use cases.
NEARの2025年以降の進路は、主要なユースケース全体での採用の成長を図りつつ、技術的ロードマップを実行するかどうかにかかっています。
The launch of stateless validation in August 2024 marks an important milestone for NEAR Protocol, but it is by no means the end state of the protocol. There is still a lot of ambitious work to be done. Long-term improvements that the team intends to work on starting in early 2025 include transaction priority fees, leaderless consensus, and sharded smart contracts.
NEARプロトコルにおける2024年8月のステートレス検証の開始は重要な節目を示しますが、決してプロトコルの最終状態ではありません。まだ多くの野心的な作業が残されています。2025年初頭からチームが取り組む予定の長期的な改善には、トランザクション優先手数料、リーダーレスコンセンサス、シャーディングスマートコントラクトが含まれます。
The transaction priority fee mechanism would allow users to pay extra for faster processing during periods of network congestion, creating a market-based approach to resource allocation. Leaderless consensus would make the network less sensitive to validators being offline, improving stability during upgrades. Sharded smart contracts would allow a smart contract to be sharded, existing on all shards simultaneously, unlocking use cases that are not possible today and making it possible to build dApps with hundreds of millions of users on NEAR.
トランザクション優先手数料メカニズムにより、ユーザーはネットワーク混雑時により迅速な処理に追加料金を支払い、資源配分に市場ベースのアプローチを導入できます。リーダーレスコンセンサスにより、ネットワークはバリデーターがオフラインになることに対してより敏感でなくなり、アップグレード中の安定性が向上します。シャーディングスマートコントラクトは、スマートコントラクトをシャード化し、すべてのシャードで同時に存在させることで、今日存在しないユースケースを解禁し、NEAR上で数億のユーザーを持つdAppsを構築することを可能にします。
Dynamic resharding represents a key goal. The new method of resharding will be quite fast and will lay the groundwork for dynamic resharding. Starting in early 2025, planning for the next phase of NEAR scalability and sharding will begin, including on dynamic resharding, the holy grail of sharding, where the network dynamically adjusts the number of shards based on the load. This would allow NEAR to automatically scale up during high usage and scale down during quiet periods, optimizing resource allocation.
ダイナミックリシャーディングは主要な目標を表しています。この新しいリシャーディングの方法は非常に高速で、ダイナミックリシャーディングの基盤を固めます。2025年初頭に、NEARのスケーラビリティとシャーディングの次のフェーズの計画が開始され、そこで負荷に基づいてネットワークがシャード数を動的に調整することが含まれる、シャーディングの聖杯であるダイナミックリシャーディングが目指されます。これにより、NEARは高い使用時に自動的にスケールアップし、静かになった際にはスケールダウンを行い、資源配分を最適化します。
The AI-native blockchain positioning could prove prescient. NEAR Protocol outlined its strategic pivot to AI, backed by a 20 million dollar fund for AI development and partnerships, aiming to leverage its sharding technology for high-speed, low-cost AI applications. If artificial intelligence and blockchain converge as NEAR anticipates, the protocol is positioning itself as foundational infrastructure for this emerging category.
AIネイティブブロックチェーンの位置付けは先を見越したものである可能性があります。NEARプロトコルは、AI開発とパートナーシップのための2,000万ドルの基金を背景に、AIへの戦略的転換を示し、高速かつ低コストなAIアプリケーション向けにシャーディング技術を活用することを目指しています。人工知能とブロックチェーンがNEARの予想通りに融合する場合、プロトコルはこの新興カテゴリの基盤インフラストラクチャとしての位置を確立します。
Cross-chain ambitions continue expanding. NEAR Intents, a system for cross-chain swaps and liquidity aggregation, recently integrated Sui and Aptos. Upcoming upgrades focus on expanding Chain Signatures to enable single-account access across 15-plus blockchains. This chain abstraction vision, where users interact with multiple blockchains through a unified interface, could reduce friction significantly if successfully implemented.
クロスチェーンの野望は拡大を続けています。NEAR Intentsは、クロスチェーンスワップと流動性アグリゲーションのシステムで、最近SuiとAptosを統合しました。今後のアップグレードは、15以上のブロックチェーンでの単一アカウントアクセスを可能にするために、Chain Signaturesの拡張に焦点を当てています。このチェーン抽象化のビジョンでは、ユーザーが統一されたインターフェースを通じて複数のブロックチェーンとやり取りするため、成功すれば摩擦を大幅に減らすことができます。
Institutional adoption presents growth opportunities. Institutional adoption advanced with Bitwise's NEAR Staking ETP launch and BitGo adding support for NEAR-native stablecoins. As traditional finance increasingly embraces crypto, infrastructure that simplifies custody and staking could attract significant capital.
機関投資家の採用は成長の機会を提供します。BitwiseのNEAR Staking ETPの開始やBitGoのNEARネイATIVEステーブルコイン対応の追加により、機関投資家の採用が進展しました。従来の金融がますます暗号通貨を受け入れる中、カストディとステーキングを簡素化するインフラストラクチャは多大な資本を引き付ける可能性があります。
The path to one billion users guides long-term strategy. In less than four years since launching mainnet, the NEAR network has over 110 million users, a great achievement for the ecosystem. But the goal for NEAR is to onboard a billion people to the User-Owned Internet. Achieving such widespread usage will require an even more scalable, performant, secure and fast protocol. While ambitious, this target frames development priorities around mass-market usability.
10億人のユーザーを目指す戦略が長期的な指針となります。メインネットを開始してから4年未満で、NEARネットワークは1億1,000万人以上のユーザーを抱えており、エコシステムにとって大きな成果です。しかし、NEARの目標は、10億人をユーザー所有のインターネットに迎え入れることです。このような広範な普及を達成するには、よりスケーラブルで高性能、安全で高速なプロトコルが必要です。野心的な目標ですが、この目標は大規模市場での使いやすさを中心に開発の優先順位を設定しています。
Conclusion: NEAR's Position in the Blockchain Landscape
NEAR Protocol occupies a distinctive position in the competitive Layer-1 blockchain landscape. Its technical innovations in sharding and consensus deliver genuine scalability improvements that address blockchain's core challenges. The protocol's focus on developer accessibility and user experience reflects understanding that technology alone cannot drive adoption.
競争の激しいレイヤー1ブロックチェーンの風景において、NEARプロトコルは独自の位置を占めています。シャーディングとコンセンサスにおける技術革新により、ブロックチェーンの核心的な課題に対応する真のスケーラビリティ改善を提供します。プロトコルの開発者のアクセス性とユーザエクスペリエンスへのフォーカスは、技術だけでは普及を促進できないという理解を反映しています。
The numbers tell a story of meaningful traction. With 46 million monthly active users, over 1,200 active decentralized applications, and approximately 2,500 active developers, NEAR has built genuine utility rather than merely speculation. The protocol processes real transactions for real users across gaming, social, DeFi and emerging AI categories.
数値は有意義な勢いを示しています。NEARは月間4,600万のアクティブユーザーを持ち、1,200以上のアクティブな分散型アプリケーションと約2,500のアクティブ開発者を擁しており、単なる投機ではなく真の利用価値を築いています。プロトコルは、ゲーム、ソーシャル、DeFi、および新興AIカテゴリーにわたる実際のユーザー向けの実際のトランザクションを処理しています。
However, NEAR operates in a brutally competitive environment where network effects favor established platforms. Ethereum's dominant developer ecosystem and Solana's momentum in high-performance applications create headwinds that technical superiority alone cannot overcome. NEAR must continue innovating while simultaneously growing its ecosystem faster than competitors.
しかし、NEARはネットワーク効果が既存のプラットフォームに有利に働く、競争の激しい環境で運営されています。Ethereumの支配的な開発者エコシステムと、高性能アプリケーションでのSolanaの勢いが、単なる技術的優越だけでは克服できない逆風を生み出しています。NEARは革新を続けると同時に、競争相手よりも迅速にエコシステムを成長させる必要があります。
The strategic pivot toward AI-native blockchain capabilities represents a calculated bet on emerging use cases. If artificial intelligence integration with blockchain proves as transformative as NEAR's leadership anticipates, the protocol is well-positioned. If not, NEAR has built robust general-purpose infrastructure that can support a wide range of decentralized applications.
AIネイティブブロックチェーン機能への戦略的転換は、新たなユースケースに対する計画的な賭けを表しています。人工知能とブロックチェーンの統合がNEARの指導者が予想するように変革的であることが証明されれば、プロトコルは好位置につけています。そうでなくとも、NEARは広範な分散型アプリケーションを支援できる堅牢な汎用インフラストラクチャを構築しました。
Looking forward, NEAR's success depends on execution across multiple dimensions: delivering on ambitious technical roadmap items like dynamic resharding and sharded smart contracts, growing the developer ecosystem through improved tooling and incentives, expanding cross-chain capabilities to become essential interoperability infrastructure, attracting institutional adoption through improved custody and staking solutions, and maintaining network security and stability as usage scales.
先を見据えると、NEARの成功は多次元の実行に依存しています: ダイナミックリシャーディングやシャーデッドスマートコントラクトのような野心的な技術ロードマップ項目の実行、ツールとインセンティブの改善による開発者エコシステムの成長、重要な相互運用性インフラストラクチャに成長するためのクロスチェーン能力の拡大、改善されたカストディとステーキングソリューションを通じた機関採用の誘致、使用が拡大するにつれてネットワークセキュリティと安定性の維持です。
The tokenomics debate over inflation reduction signals ecosystem maturity. By moving from growth-at-all-costs to sustainable economics, NEAR demonstrates recognition that long-term value requires more than aggressive token incentives. The proposed reduction to 2.5 percent inflation represents a balancing act between validator incentives and token value preservation.
インフレーション削減に関するトークノミクスの議論はエコシステムの成熟を示唆します。コストに頼らない成長から持続可能な経済へと移行することで、NEARは長期的価値には積極的なトークンインセンティブ以上のものが必要である認識を示しています。提案された2.5%のインフレーション削減は、バリデーターインセンティブとトークン価値の保全のバランスを示しています。
For investors and developers evaluating NEAR, the protocol offers genuine technological innovation, meaningful current usage, and ambitious plans for future growth. However, it faces intense competition from better-established platforms and must prove it can capture meaningful market share from incumbents. NEAR's journey from machine learning startup to blockchain infrastructure platform reflects the adaptability and technical excellence of its founding team. Whether that proves sufficient to secure a lasting position among blockchain's top platforms remains to be written.
NEARを評価する投資家および開発者にとって、このプロトコルは真の技術革新、有意義な現在の使用、および将来の成長のための野心的な計画を提供します。しかし、それはより確立されたプラットフォームからの激しい競争に直面しており、既存のプラットフォームからの有意義な市場シェアを獲得できることを証明する必要があります。機械学習スタートアップからブロックチェーンインフラストラクチャプラットフォームへのNEARの旅は、その創設チームの適応性と技術的卓越性を反映しています。それがブロックチェーンのトッププラットフォームにおける持続的な地位を確保するのに十分かどうかはまだ記されていません。
The blockchain industry has not crowned winners in the Layer-1 competition. Multiple platforms will likely coexist, serving different use cases and user preferences. NEAR has earned its position in this multi-chain future through technical merit and ecosystem development. Its ultimate success depends on continued execution, market conditions, and perhaps some measure of timing and luck that affects all ambitious technology ventures.
ブロックチェーン業界はレイヤー1の競争においていまだ勝者を決定していません。複数のプラットフォームが共存し、異なるユースケースとユーザーの好みに応じる可能性があります。NEARは技術の優位性とエコシステム開発を通じてこのマルチチェーンの未来における地位を獲得しました。その最終的な成功は、継続的な実行、マーケットコンディション、そして恐らく友好なタイミングや運の測定が全ての野心的な技術事業に影響を与えるという。