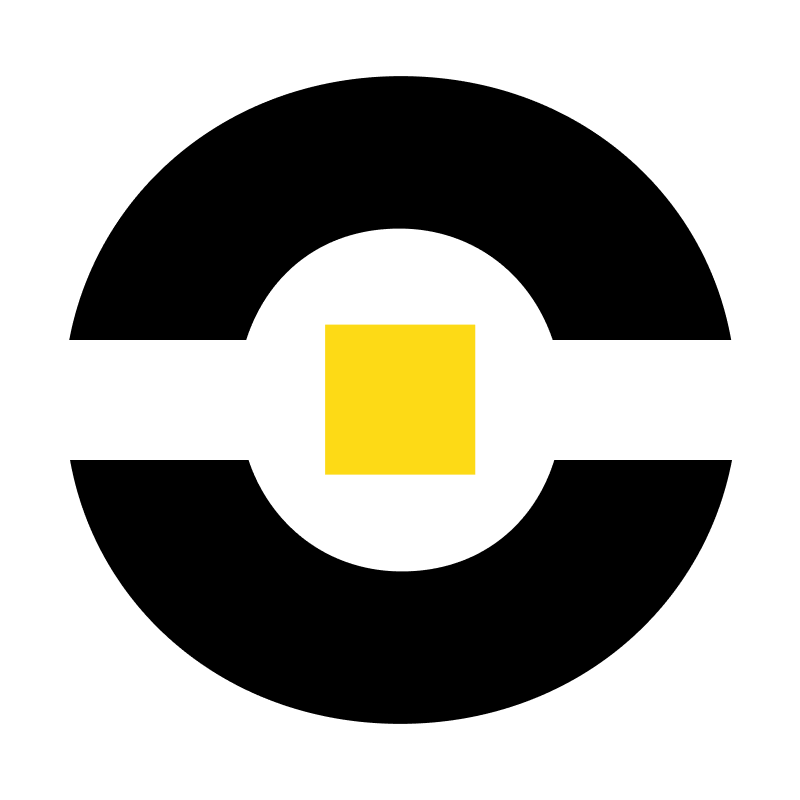Sei
SEI#105
Seiとは?
Seiは高スループットなレイヤー1ブロックチェーンであり、スケール時のEVM実行を制限する実務上のボトルネック――主にトランザクションの逐次処理、慎重なコンセンサス設定がもたらすレイテンシ、そしてステート/ストレージのオーバーヘッド――を軽減することで、Ethereum互換アプリケーションをより高速かつ低コストで動作させることを目的として設計されています。その中核となる「モート(参入障壁)」は、単なる新規性ではなく、敵対的環境下でのパフォーマンスを最優先するエンジニアリング姿勢にあります。つまりSeiの本番ネットワークは、並列実行(Sei v2 parallelized EVM で導入)と、プロトコルの公式資料で Twin Turbo Consensus と表現される、強く最適化されたTendermint派生のBFTコンセンサススタックをEVM環境と組み合わせ、Ethereumの確率的最終性ではなくサブセカンドの決定論的最終性を目標としています。
マーケット構造の観点では、Seiは「何でもできる汎用L1」というよりも、レイテンシに敏感なオンチェーン・ファイナンスに最適化された実行レイヤーとして自らを位置付けつつ、広義のEVM系L1競合とも正面から競争してきました。2026年初頭時点の公開マーケットデータ・アグリゲーターでは、時価総額ベースでSEIは大型暗号資産の中では中位〜下位レンジに位置づけられており(たとえば CoinMarketCap では、日次や算出方法によって #70〜#80 前後に表示されることがあります)、これは主として流動性と取引所上場状況の代理指標として意味を持つのであって、プロダクトマーケットフィットの本質的な指標というわけではありません(CoinMarketCap)。
利用状況については、サードパーティのアナリティクスダッシュボード上で、チェーンのDeFi資本規模と比較すると非常に高いトランザクション数やアクティブアドレス数が観測される局面が断続的に見られてきました。DuneのSeiチェーンページでは、週次トランザクションが数千万件規模、週次アクティブアドレスがスナップショットによっては100万近くに達するケースがある一方で、DeFiLlamaが示すTVLはボラティリティこそ高いものの、信仰ではなく計測可能な採用シグナルとして扱われています。
Seiは誰がいつ創設したのか?
SeiはCosmos/Cosmos-SDK系譜から生まれ、2023年に初期メインネット期(プロジェクトのコミュニケーションではしばしば「Pacific-1 Mainnet」と呼称)をローンチしました。当時の業界環境は、2022年以降のリスクオフムード、米国での取引所・規制不透明感、そして「夢のあるホワイトペーパー」よりも「具体的なスループット実績」を評価する資金調達環境に強く影響されていました。
プロジェクトの発信によれば、このネットワークは2023年メインネットを土台としつつ、2024年7月のSei v2アクティベーションとEVMへの大きな舵切りを経て、実行プロファイルを大きく変化させてきました(Sei community airdrop background; Sei v2 announcement)。公式資料で最も一貫して言及される開発主体はSei Labsであり、広報や技術ロードマップでは共同創業者のJay Jogが表に立つことが多くなっています。
時を経るにつれ、ストーリーは「トレーディング特化チェーン」から「高性能なEthereum互換の決済レイヤー」へとシフトしてきました。これは、EVMが持つ開発者分布とツールチェーン自体が一種のロックインであるという、現実的な認識を反映しています。
この進化は、Sei LabsのSIPプロセスなどガバナンス寄りのコミュニケーションにも明示的に表れています。そこでは、複数の実行環境を抱える構造から「EVMオンリー」な方向へアーキテクチャを簡素化し、開発・インフラ・コンポーザビリティをEthereum標準に揃えることが検討されています。言い換えると、Seiの「物語」は全面的な路線転換というより、「何に最適化すべきか」の焦点を徐々に狭めてきたプロセスです。すなわち、EVM実行速度と予測可能な最終性を最重視し、そのために初期のCosmosネイティブなスマートコントラクト経路を段階的に廃していくという選択です。
Seiネットワークはどのように機能するのか?
SeiはTendermint系のビザンチン耐性(BFT)コンセンサスコアを用いるプルーフ・オブ・ステークネットワークであり、Nakamoto型の確率的な決済ではなく、BFT設計で一般的な決定論的(単一ブロック)最終性を持ちます。プロトコルドキュメントでは、現在のコンセンサス実装を「Enhanced Tendermint BFT」と記述し、Twin Turbo Consensusとしてマーケティングしています。ターゲットブロックタイムは約400msで、標準的なBFTセーフティ閾値としてバリデータの3分の2以上の合意を要件としています。実際の応用面での主張としては、高速かつ決定論的な最終性は単なるUX改善にとどまらず、再編成リスクや最終性の遅延が経済的コストとして顕在化しやすいパーペチュアル、CLOB型設計、清算依存度の高いレンディングなど、レイテンシに敏感なDeFiプリミティブにとって構造的な有利性になるというものです。
技術的には、Seiの差別化は単一の「ブレイクスルー」ではなく、複数のパフォーマンス最適化を積み上げたスタックとして理解するのが適切です。実行レイヤーでは、ネットワークは並列化されたEVM処理――競合しないトランザクションを同時に実行する――を強調しつつ、既存のEVMコントラクトやツールとの互換性を保つためにEthereumのオペコードおよびガスセマンティクスを維持しています。
コンセンサス進化の面では、Seiの「Giga」ロードマップが明示的に、さらなる桁違いのスループット向上を狙っており、最適化されたTendermintネットワークでもボトルネックとなり得る単一プロポーザ制約を緩和するため、マルチプロポーザ型BFT設計(「Autobahn」)への移行を掲げています。
セキュリティ面では、こうしたパフォーマンス目標は依然としてバリデータの分散性と運用レジリエンスに依存します。Seiのステーキングドキュメントには、Cosmos周辺チェーンとしてはやや異例の設計選択が明記されています。すなわち、「資金のスラッシングは行わない」としつつ、ジェイリングや報酬除外をエンフォースメント手段として用いると記載しており、直接的な資本ペナルティよりも、ライブネスインセンティブと評判経済に重心を置いたセキュリティモデルになっています。
SEIトークンのトークノミクスは?
SEIは最大供給量100億枚でキャップされた資産であり、2026年初頭の一般的なデータアグリゲーターでは流通供給量はその上限を大きく下回っています。これは、まだアンロック/ベスティングされていない分や未発行リザーブのオーバーハングが相当量残っていることを示唆しており、投資家はそれを「将来のアップサイド」というより希薄化リスクとしてモデル化するのが一般的です。
ネットワークのセキュリティとバリデータ経済は、設計上ステーキングを基盤としており、少なくともネットワークのブートストラップおよび成熟フェーズにおいては継続的なエミッションが前提になります。サードパーティのトークノミクス概要では、ステーキング報酬は初期にはリザーブから、後にはインフレ的な新規発行によって賄われると説明され、インフレ率は期間によって変動してきたと報告されています。ただし、具体的なパラメータはガバナンスおよび実装に依存するものであり、不変のものとして扱うべきではありません。
ユーティリティおよび価値捕捉の仕組みは分かりやすい一方で、必ずしも「ETHライク」というわけではありません。SEIはトランザクション実行の手数料トークンであり、コンセンサスを担保するステーキング資産として機能します。しかし、EIP-1559以降のEthereumとは異なり、Seiは手数料バーンによるデフレメカニズムを備えたコモディティとして自らを位置づけてはいません。公式サポート資料では、EIP-1559以前型のガスモデルを採用し、トランザクション手数料はバーンされずにバリデータへ分配されると説明しており、これは経済的な利益が供給削減ではなく、バリデータ/デリゲータの利回りに集中する構造になっていることを意味します(Seiサポート:手数料モデルとバーンなし)。
実務的には、「バーンナラティブ」よりもステーキング利回り、バリデータセットの健全性、実際の手数料収益の創出が、ファンダメンタルな評価フレームワークの中心となります。同時に、PoS共通の論点として、「有機的な手数料収益が、セキュリティを損なうことなく、将来的にどの程度までエミッション需要を代替できるか」という問題も残ります。
誰がSeiを使っているのか?
Sei上の利用状況を見る際には、投機的な流動性と実際のオンチェーン・ユーティリティを分けて考える必要があります。高いトランザクション数は、実需だけでなく、インセンティブプログラム、エアドロップファーミング、ゲームやコンシューマーアプリ特有のパターンなどが複合的に寄与し得るからです。エコシステムの公式コミュニケーションやサードパーティアナリティクスは一貫して、Seiのコアな強みを「スループットと低レイテンシ決済を活かしたDeFi」に置いており、各種ダッシュボード上ではトランザクション数とアクティブアドレス数において一定規模の活動が確認される一方で、TVLは時期によって大きく変動してきました。これは、暗号資産において「ユーザー」と「資本」が必ずしも同じペースで伸びるわけではないことを改めて示すものです(DuneのSeiアクティビティなど)。
DeFiの内部だけを見ても、「TVLに対して大きなパーペチュアル取引高」という「資本効率」面が強調されることがあります。これは「トレーディングチェーン」という仮説を方向性としては支持する一方で、出来高がインセンティブ、相場環境、少数の支配的な取引 venue に強く依存し、可変的であることも同時に思い出させます。
Seiの採用ストーリーがより機関投資家にも理解しやすい形になるのは、噂に頼らずに言及できる、現実世界資産(RWA)やファンドトークン化に関するパートナーシップの領域です。Seiエコシステムからの発表や暗号資産系メディアは、規制されたトークン化インフラとの連携を報じており、たとえばSecuritizeがApolloのクレジット戦略(ACRED)にリンクしたトークン化フィーダー商品をSeiにもたらしたケースでは、コンプライアンス管理および適格投資家向けアクセスに焦点が当てられています。
これとは別に、KAIOのSeiへの展開もプロジェクト側の発表とCoinDeskの双方で取り上げられており、BlackRock関連の流動性商品やBrevan Howardのフィーダー構造といった大手運用会社の戦略へのトークン化エクスポージャーを、リテール一般ではなく、規制されたラッパーを通じて機関/適格投資家に提供するものとして説明されています。これらは「大手機関がSEIを財務資産として保有している」という話とは別物ですが、汎用的な「エコシステム提携」よりも、実際のプロダクション統合としては信頼性の高いシグナルだと言えます。
Seiのリスクと課題は?
Seiに対する規制上のエクスポージャーは、特定の個別強制執行事例に直結するというよりも、主に制度・レジームベースの間接的なものです。それでも重要なのは、米国がこれまで、一部のプルーフ・オブ・ステーク型トークン配布やステーキングサービスをめぐるスキームを問題領域として扱ってきたという事実です。 scrutiny(精査・監視)。規制上の「隣接領域(regulatory adjacency)」の具体例として、ステーキングされた SEI エクスポージャーを米国上場ビークルの中にラップしようとする試みがある。Canary Capital は 2025年4月30日に「Canary Staked SEI ETF」の登録届出書を提出し、その後 2025年12月10日に修正 S-1/A を提出した。2026年初頭時点で、その記録は本質的に承認済みプロダクトではなく「届出および修正」が行われた状態にとどまっており、有効化までの道のりは SEC のプロセスおよび市場構造上の制約に依存している(SEC S-1 filing; SEC S-1/A amendment)。
別の観点として、中央集権化ベクトルはすべての PoS ネットワークに存在し、ステークの集中、バリデータ運用の同質化、少数のインフラプロバイダへの依存といった形で顕在化しうる。Sei が「ノースラッシング(no slashing)」を明記した決定は、極端な状況下で特定のバリデータ不正行為に対して、ジェイル(隔離)と報酬喪失だけで十分な抑止力となるのかという懐疑的な問いも同時に生む。
競争リスクは深刻である。というのも、Sei の主張は「新しい機能」ではなく「EVM 互換性を備えた優れたパフォーマンス」であり、まさに潤沢な資本を持つエコシステム同士が競い合っている戦場だからである。関連するピアセットには、差別化された実行モデルを持つ他の高スループット L1(Solana)、並列実行もしくは Move ベース L1(Aptos, Sui)、そしてコスト・流動性・ディストリビューションを軸に競合する EVM 中心の高性能チェーンおよびロールアップが含まれる。
経済的な脅威も、こうした競争から生じる。もし流動性、ステーブルコイン厚み、開発者のマインドシェアが他所に集中していくなら、多くのアプリケーションが第一にユーザーと資本、第二にレイテンシを最適化することを踏まえると、パフォーマンス優位だけでは不十分になりうる。逆に、Sei のアクティビティがインセンティブ設計や少数の支配的アプリケーションに過度に依存している場合、それらのインセンティブが薄れたり、競合するプラットフォームが移転を補助金で支援したりすると、利用状況に反射的なドローダウンが生じうる。
What Is the Future Outlook for Sei?
Sei の短期から中期にかけてのロードマップは、到達を目指すパフォーマンス指標と、それを達成するために必要と考えるアーキテクチャ上のワークストリームを、珍しいほど明確に示している。ネットワークの公式な “Giga” メッセージングでは、実行・コンセンサス・ストレージを再設計し、新たな EVM クライアントを構築するとともに、単に調整された Tendermint のパラメータに頼るのではなく、コンセンサスをマルチプロポーザ型 BFT アプローチ(Autobahn)へ移行することで、EVM ワークロードに対して概ね「50倍」のスループット向上を目標としている、と位置付けている。
並行して、SIP-3 のようなガバナンス提案は、チェーンの開発者向けサーフェスを EVM ファースト、あるいは EVM 専用の姿勢へと単純化しようとする意図を示している。これは複雑性とフラグメンテーションを低減しうる一方で、Cosmos ネイティブなステークホルダーを疎外したり、残存する非 EVM アプリケーションに移行コストを生じさせたりするリスクも伴う。
構造的なハードルは、「web2 レベルのパフォーマンス」は単なるエンジニアリング上の主張ではない、という点にある。それは分散性の制約、敵対的な MEV 条件、バリデータの入れ替わり、そして実アプリケーション間のコンポーザビリティの下でも成立し続けなければならない。仮に Sei が生のスループットを達成したとしても、持続的な採用を支えるには、ディープなステーブルコイン流動性、信頼できる RWA 発行レール、防御可能なバリデータ/インフラ基盤が技術ロードマップと共進化できるかどうかが重要になる可能性が高い。
Sei が金融グレードのワークロードをターゲットにすればするほど、金融グレードの期待値を引き継ぐことになる。すなわち、予測可能な実行、運用上のレジリエンス、規制資産に対応しうるコンプライアンス互換のオンランプ、そしてエコシステムを分断することなくコアパラメータを変更できるガバナンスプロセスである。