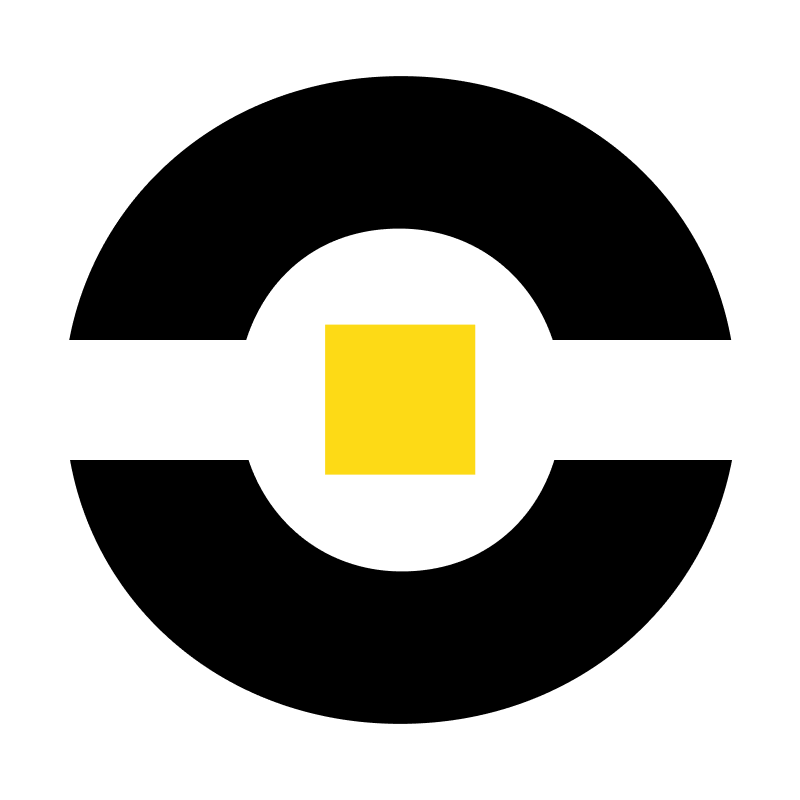Ethereum は、メインネットのブロックガス上限が11月25日に6,000万へ到達し、この4年間で最高水準となる実行キャパシティの新たな節目を迎えた。これにより、ベースレイヤーの処理能力は1年でほぼ2倍となった。
この調整は、51万3,000以上のバリデータが上限引き上げへの賛同を示し、Ethereumのコンセンサスルールで求められる50%超の閾値を上回ったことで自動的に適用された。
Ethereum FoundationのリサーチャーであるToni Wahrstätterは、この節目を、ベースレイヤーでのトランザクションスループット拡大を目指した1年間にわたるコミュニティの取り組みの集大成だと説明している。タイミングも象徴的で、Ethereumは12月3日にFusakaハードフォークを控えており、PeerDASやデータ可用性を飛躍的に高めるための追加スケーリング基盤が導入される予定だ。
ガス上限の引き上げは、より広いEthereumエコシステムが、L2インフラ全体で毎秒2万4,000件超のトランザクション処理速度を最近記録した局面で行われたものであり、スケーリングソリューション採用の加速を示している。
何が起きたのか
ガス上限が4,500万から6,000万へ引き上げられたことで、ブロックキャパシティは33%拡大し、トークン送金、スマートコントラクト実行、分散型取引所(DEX)スワップなど、1ブロック当たりに処理できるトランザクションが増加した。バリデータは各自がノード設定を変更してより高い上限への支持を表明し、多数派の閾値を超えた段階で自動的に上限引き上げが発動された。
ブロックチェーンリサーチャーのZhixiong Panは、この引き上げを可能にした3つの技術的改善の収束を指摘している。EIP-7623 によるプロトコルレベルのcalldataコスト調整で最悪ケースのブロックサイズを抑制できるようになったこと、NethermindやErigonなど複数クライアントでの最適化により、パフォーマンス低下なく6,000万ガスのブロックを処理できるようになったこと、そして数カ月に及ぶテストネット検証で、負荷増大時でもEthereumの4秒コンセンサスウィンドウ内で安定したブロック伝播が確認されたことだ。
ガス上限はそれまで約4年間にわたり3,000万前後に据え置かれていたが、コミュニティは2024年3月からネットワークキャパシティ拡張に向けた動きを開始した。Ethereum開発者のEric ConnorとMariano Contiは、バリデータやソロステーカー、クライアント開発チームを巻き込み、高スループットを目指す「Pump The Gas」キャンペーン を立ち上げた。このムーブメントは2024年12月にバリデータのシグナル増加とともに勢いを増し、2025年11月の今回の有効化に結実した。
この期間中、L2スケーリングネットワークは大きな成長を遂げた。GrowThePieのデータによると、Ethereumエコシステム全体のTPS(1秒あたりトランザクション数)は最近、ピーク時に24,192を記録し、永久先物プラットフォームLighterが約5,035 TPS、Baseが137 TPSを占めた。全L2ネットワークの7日平均は364.52 TPSで、L2ソリューションは現在、Ethereumエコシステム全体のトランザクション活動のおよそ95%を担っている。
関連記事: Ethereum Surges Above $3,000 As Technical Indicators Signal Potential For Gains
なぜ重要なのか
ガス上限の拡大は、スケーリング基盤が正念場を迎えるなかで、Ethereumベースレイヤーの根本的な制約に対処するものだ。ガス上限が高くなることで、需要急増時の混雑が緩和され、より多くの経済活動をメインネット上で直接清算できるようになる。また、dAppは極端なガス効率化を強いられることなく動作できる余地が広がる。開発者にとっては、スマートコントラクトにおける過度なガス最適化が不要になり、よりシンプルなコードと迅速なデプロイが可能になることを意味する。
Ethereum共同創設者のVitalik Buterinは、今後のスケーリングについて、一律のキャパシティ拡張ではなく、よりターゲットを絞ったアプローチを取るべきだと示唆している。具体的には、さらなるガス上限引き上げと同時に、重量級プリコンパイルや複雑な算術オペコード、特定のコントラクト呼び出しといった計算コストの高い処理のガスコストを引き上げることを提案している。この方法論は、バリデータの効率性とネットワークセキュリティを維持しつつ、実効的なブロックサイズの拡大を可能にし、新たな攻撃ベクターや中央集権化圧力を生まない形でキャパシティ増強を持続させる狙いがある。
Fusakaアップグレード とのタイミングも戦略的だ。12月3日21:49 UTC、スロット13,164,544での有効化が予定されているFusakaでは、Ethereumの長期的なスケーリングロードマップに不可欠だとButerinが位置づけるPeerDAS(データ可用性サンプリングの再設計プロトコル)が導入される。PeerDASは、バリデータがブロブ全体をダウンロードする代わりにサンプリングによってブロブデータの可用性を検証できるようにし、帯域幅要件を大幅に低減するとともに、ブロブキャパシティの大幅な拡張を可能にする。
Fusaka本体の有効化後、Ethereumは「Blob Parameter Only」フォークを通じて段階的にブロブスループットを拡大していく。BPO1ではブロック当たりブロブターゲットを10、最大値を15に引き上げ、BPO2ではこれを14と21までさらに増加させる計画だ。Ethereum Foundationは、メインネット実装前に脆弱性を洗い出すため、9月15日から10月13日にかけてSherlockプラットフォーム上で、GnosisとLidoが共催する総額200万ドル規模の監査コンテスト を実施した。
最後に
ガス上限6,000万への引き上げと目前に迫るFusakaアップグレードは、Ethereumインフラをベースレイヤーとデータ可用性レイヤーの両面からスケールさせるための協調的な取り組みを示している。ネットワークは、成長よりも安定性を優先した慎重な姿勢から、広範なテストネット検証とクライアント最適化に裏打ちされたデータ重視の戦略へと移行している。
とはいえ、長期的な非中央集権性をめぐる懸念は残る。ブロックが大きくなれば、ノード運用により高性能なハードウェアが必要となり、参入障壁が高まることで時間の経過とともに検証作業が集中する可能性がある。現時点のデータではネットワークは安定しているものの、一部の開発者はすでに1億ガスへのさらなる引き上げについて議論を始めており、その場合はステート成長、暗号処理負荷、ネットワークデータフローを慎重に管理する必要がある。
L1キャパシティ拡張とL2採用の関係も依然としてオープンクエスチョンだ。よりスケーラブルなベースレイヤーはロールアップへの需要を減らすという見方もあれば、より強固な決済レイヤーを提供することでエコシステム全体を強化するという見方もある。L2ネットワークは現在、Ethereumトランザクションの大半を処理しており、Lighter、Base、Arbitrumといったプロジェクトが大きなアクティビティを牽引している。ベースレイヤーのスケーリングがどれだけ有効かは、こうした急速に進化するインフラをどれだけうまく支えられるかによって測られるだろう。
Ethereumの開発ロードマップはFusakaで終わらない。2026年にはGlamsterdamアップグレードが予定されており、ブロックタイムの短縮やさらなるガス上限引き上げが検討されている。今後10年でベースレイヤー1万TPS、L2エコシステム全体で数百万TPSを目指すなか、6,000万ガス上限は、分散型アプリケーションのためのグローバルな決済レイヤーへと変貌を続けるEthereumにおける重要な通過点といえる。
次に読む: Financial Giants Choose Specialized Networks Over Ethereum Amid Privacy Concerns