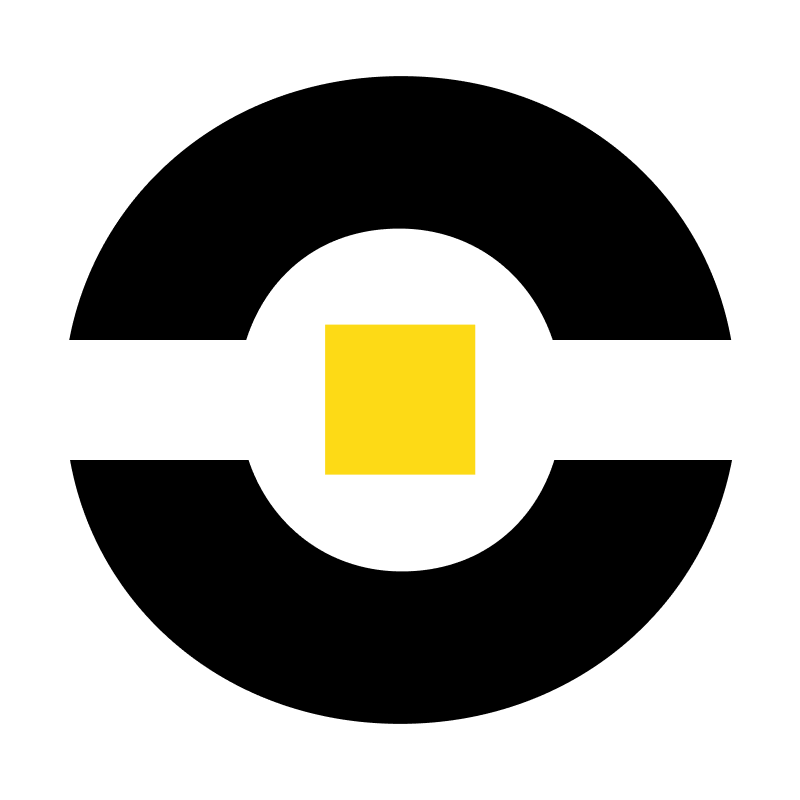ブロックチェーンはしばしばデジタル島にたとえられます。
セキュアで自己完結していますが、孤立しています。
過去10年間、様々なプロジェクトがこれらの島を橋渡しし、資産とデータをネットワーク間で移動可能にしようとしました。
しかし、初期の“ブロックチェーンを接続する”
試みは主にアドホックなブリッジまたはフェデレイティッドシステムに依存しており、新たなリスクを生み出しました。
今日、新しいパラダイムが登場しています: モジュラーブロックチェーンアーキテクチャです。このモデルでは、異なるブロックチェーン機能の層 (実行、コンセンサス、データストレージ、セキュリティ)がそれぞれ別のネットワークにより提供され、 完璧に統合されます。この動きの最前線に立っているのが、Celestia、Avail、EigenLayerという 先駆的な三つのプロジェクトです。それぞれがパズルの1つを解決し、ブロックチェーンをより接続され、 スケーラブルで多目的にするべく取り組んでいます。ここでは、これらのプロジェクトがどのように機能し、 解決を目指す問題を探り、どのように一緒にブロックチェーンエコシステムの再定義を行っているかを掘り下げます。
単一チェーンからモジュラーの未来へ
伝統的な「モノリシック」ブロックチェーン(例:ビットコイン、初期のイーサリアム)では、ネットワークの全てのノードがすべての機能を処理します: トランザクションの実行、コンセンサスの達成、データの利用可能性の確保、アップデートの最終化。 この一つの方法で全部をカバーするデザインはシンプルでセキュアですが、スケーラビリティには固有の限界があります。 すべての操作が単一の層で行われるため、使用が増えるとチェーンがボトルネックになる可能性があります。 対照的に、モジュラーブロックチェーンはこれらの義務を個別の層またはモジュールに分離します。 例えば、ある層はトランザクションの処理(スマートコントラクトの実行)だけを扱い、別の層はトランザクションの順序設定と ブロックデータが誰でも検査できるよう公開されていることを検証することのみに集中します。 これらの責任を切り離すことで、モジュラーアプローチは柔軟性とスループットの向上を 提供しながらも、セキュリティを犠牲にしないことを約束します。
モノリシックvs.モジュラーブロックチェーンアーキテクチャ。左側のモノリシックデザインにおいては、 単一のブロックチェーンが実行、決済、コンセンサス、データの取り扱いを担当します。 右側のモジュラーデザインでは、これらの機能が専門化された層に分割されます。 例えばロールアップが実行を担当し、別ネットワークがコンセンサスとデータ取り扱いを提供します。 この労働分担によって、共通のセキュリティまたはデータ層を多数のチェーンが共有することで、 スケーラビリティと相互運用性を向上させることができます。
モジュール化への移行の推進は、スケーリングの試みから得た経験が大きく影響しています。 初期段階では単一のモノリシックチェーンの容量を単純に増やす試みが行われましたが、 これは中心化リスクにつながりました(ビットコインとイーサリアムのブロックサイズに関する論争で見られたように)。 レイヤー2ソリューションのロールアップは、実行をメインチェーンから移行し、メインチェーンをセキュリティとデータストレージに使用することで登場しました。 イーサリアム上のArbitrumやOptimismなどのロールアップによって、処理能力の大幅な向上が示されましたが、 同時に別の制限も浮き彫りにしました:データの利用可能性の問題です。 ロールアップでは、それでもトランザクションデータは信頼性のあるアクセス可能な場所に投稿されなければならず、 (誰でも状態を再構築したり詐欺を挑戦できるように)しなければなりません。 忙しいレイヤー1であるイーサリアムにデータを投稿することは高価で容量が制限されており、 ロールアップのパフォーマンスを制約しています。これはCelestiaとAvailが専用データ利用可能性ネットワークで解決しようとしている問題です。
同時に、新しいブロックチェーンやサービスを開始するプロジェクトは、ゼロから新しいネットワークを確保するというブートストラップ問題に直面しています。 ブロックチェーンのセキュリティはその規則を強制するバリデーター(またはマイナー)のセットと同じくらい強力です。 PolkadotやCosmosのようなネットワークは、「共有セキュリティ」または相互運用性フレームワークを提供することでこれに取り組みましたが、 各々にトレードオフが存在します。Polkadotのパラチェーンは中央のリレーチェーンのセキュリティを共有し、 CosmosチェーンはIBCプロトコルで接続できますが、独自のバリデーターセキュリティを担当し続ける必要があります。 EigenLayerはイーサリアムでの共有セキュリティについて新しいアプローチを導入しています: 既存のイーサリアムのステイカーがその資産を「再ステーク」して追加のチェーンやモジュールを確保させることができます。 本質的に、イーサリアムの大規模なバリデーターセットのセキュリティをリサイクルして新しい暗号インフラストラクチャをブートストラップします。
これらの革新 – 専用データ利用可能性の層と共有セキュリティのための再ステーキング – は、 モジュラーでマルチチェーンのクリプトエコシステムの基盤を形成します。 ブロックチェーンは共通のデータ層にプラグインし、セキュリティリソースを共有し、 それぞれがより容易に相互運用できます。それぞれのプロジェクトを詳細に探求する前に、 モジュラーのスタックで各“層”が何を意味するかを理解することが重要です:
*実行層:トランザクションが実行され、状態が更新される場所(例:スマートコントラクトの処理するロールアップ)。 *コンセンサス層:ブロックがバリデーターよって順序設定され、最終化される場所(チェーンの“心臓”)。 *データ利用可能性層:各ブロックのトランザクションデータが発行及びアクセス可能であることを保証し、 ネットワークがそのブロックの内容を検証できるように。 *決済層(オプショナル):結果の争議解決や証明の検証を行う層で、ロールアップが詐欺証明や有効性証明を投稿して結果を解決できます。
モノリシックチェーンにおいては、これらすべての役割が1つのプラットフォーム上で統合されています。 モジュラー設計では、異なるネットワークが異なる役割を処理します。 例えば、Celestiaはコンセンサスとデータ利用可能性を提供し、多くの独立した実行層(ロールアップやアプリケーション専用チェーン)がそれに基づいて動作します。 Availも同様に、多くのチェーンに対してデータ利用可能性の役割を担います。 EigenLayerはセキュリティ側面に焦点を当てており、 複数のサービスがイーサリアムのコンセンサスから信頼を引き出すことを可能にしています。 これらを補完的な努力と考えることができる: CelestiaとAvailがスケーラブルなデータとコンセンサスを扱い、 EigenLayerが共有セキュリティと相互運用性を扱っています。それぞれを順に探求し、 その起源、機能、現状を含めて詳しく見ていきましょう。
Celestia: モジュラーデータ利用可能性の先駆者
Celestiaは、地上から設計された完全にモジュラーなブロックチェーンネットワークとしてしばしば信用されています。 2023年後半にメインネットでのベータ版として立ち上げられたCelestiaの基本的なアイデアはシンプルかつ強力で: コンセンサスとデータ利用可能性「のみ」を提供し、他のことは意図的に行わないことです。 Celestiaはユーザートランザクションやスマートコントラクトを実行しないし、 それを使用するチェーンの状態遷移さえも検証しません。 代わりに、様々なチェーン(しばしばロールアップ)によって送信されるデータのブロックを順序設定し、 そのブロックデータが誰にでもダウンロードと検証ができるように広く利用可能であることを保証します。 これらのタスクに特化することにより、Celestiaは他の多くのチェーンが 実行をオフチェーンで行うことを信頼できるベース層として機能することを目指しています。
技術的には、Celestiaの際立った特徴はデータ利用可能性サンプリング(DAS)です。 これは、軽量ノードが、全体のブロックをダウンロードすることなく ブロックデータが公開されているかを検証できる暗号化技術です。 Celestiaでは、各ブロックのデータが消失復元符号化され、小さな部分に分けられます。 軽量ノードがランダムにいくつかの部分をサンプルし、それらを取得できるかをテストします。 十分なランダムサンプルが成功すると、ノードはブロック全体のデータが 完整で利用可能であるという高い信頼感を得ます。 この方法は、個別のノードへの負担を大幅に削減し、スマートフォンやブラウザでもデータ利用可能性の確認を手助けでき、 データを隠蔽しようとする不正なバリデーターの試みを捕捉することができます。 これは、たとえば多くの独立した監査者が大きな本のランダムなページをスポットチェックするようなもので、 もし1ページでも欠けていたら、何らかの監査者がそれに気付く可能性が高いというわけです。 少なくとも幾つかの軽量ノードが誠実であり、熱心にサンプリングしている限り、 データの隠蔽は検出されずにほとんど不可能になります。
Celestiaのメカニズム下での消失復元符号化とKZGポリノミアルコミットメントのおかげで、このサンプリングが可能になっています。 消失復元符号化はデータに冗長性を追加します: たとえブロックの一部が欠けていても、符号化された部分から元のデータを再構成できます。 KZGコミットメントは(イーサリアムが後にそのプロトダンクシャーディングアップグレードのために採用したのと同じ数学)、 データ部分が正しいオリジナルの多項式に対応しているというコンパクトな証明を可能にし、 軽クライアントがサンプルを迅速に検証できるようにします。 これらの技術により、Celestiaは典型的なブロックチェーンよりもはるかに大きなブロックサイズを安全にサポートできます。 メインネット「ベータ」ローンチ時(2023年10月、コードネームはLemon Mint)、 Celestiaは既にイーサリアムの約0.1 MBブロックに比べて遥かに大きい2–8 MBまでのブロックを取り扱い始めています。 実際、Celestiaのロードマップは1000 MB(1 GB)ブロックへのスケーリングを視野に入れており、 総合的には毎秒数万件のトランザクションをサポート可能です。 2025年4月にCelestiaのテストネットは128 MBブロックを用いて約21 MB/sのスループットを実現するなど、 印象的なスループットを示しています。
この設計は逆説的な性質さえ示しています: 多くの軽量ノードがデータのサンプリングに参加するほど、ブロックが安全に広がることができます。 言い換えれば、非バリデーター(軽クライアント)を追加することで実は ネットワーク容量が増加し、分散化による新しい形のスケーラビリティがもたらされています。
なぜデータが利用可能であることを保証するためにそこまでの手間をかけるのか? Celestiaのメリットは、ブロックチェーン(やロールアップ)を新たにデプロイするのを容易にし、 独自のバリデータネットワークを立ち上げたりデータ利用可能性の限界を心配する必要がないことです。 開発者はどんな実行ロジックでもロールアップを作成できます: EVMのスマートコントラクト、ゲーム用のチェーン、プライバシー重視のチェーンなど。 これらがそのトランザクションデータをCelestiaに投稿することが可能です。 Content: ブロックスペースは豊富で安価です。単一のチェーンで限られたスループットを競うのではなく、多くの専門化されたチェーンが並行して稼働し、すべてがCelestiaによって支えられています。開発者はもはや、他人のチェーンにアプリを無理やり合わせたり、Layer-1をクローンしてバリデータをゼロから募集したりする必要がありません。Celestiaのコンセンサスとデータレイヤーに接続するソブリンチェーンを開始できます。
特に重要なのは、Celestiaは自分の力で動くチェーンに対して何らの実行ルールも強制しないことです。つまり、Celestiaはロールアップの不正証明や有効性証明を確認しません。それらはロールアップのユーザー、もしくは存在する場合は別の決済レイヤーによって処理されます。このアプローチは「ソブリンロールアップ」と呼ばれ、ロールアップが自らの状態に対してソブリンです(不正行為を自動的に罰する上位機関はありません)。Celestiaを利用するソブリンロールアップが不正な状態遷移を生成した場合でも、Celestiaのバリデータはデータが適切にフォーマットされている限り、そのデータを含めて公開します。Celestiaの仕事は、そのロールアップにおいて何が有効か無効かを知ることではありません。それはロールアップコミュニティやオプションの決済レイヤーにかかっています。この設計はCelestiaの中立性とシンプルさを最大化しますが、それによりロールアッププロジェクトは選択を迫られます:完全にソブリン(社会的合意によっていかなる欠陥も処理)することも、自身の不正証明を導入することも可能です、またそれらを何らかのセキュリティレイヤーに投稿することもできる(場合によってはEthereumや他のチェーンにも)。実際には、いくつかのチームがデータにはCelestiaを、決済レイヤーにはEthereumを使用する計画を立てており、ハイブリッドモデルを実現しています。Ethereumがセキュリティのために証明を検証し、Celestiaがより安価なデータ可用性を提供するというものです。CosmosベースのロールアップであるEclipseは、データにはCelestia、実行にはSolanaのVM、決済にはEthereumを検討した一例であり、モジュラーなアーキテクチャが可能にするクリエイティブな組み合わせを示しています。Celestia自体はCosmos SDKで構築され、Tendermint(現在のCometBFT)コンセンサスアルゴリズム(PoSベース)を使用しています。100以上のバリデータが稼働しており、特定のロールアップデータをブロックから効率的に取得できるよう、ネームスペース付きマークルツリーといった機能を実装しています。2023年のアップグレードでは、ネットワークは即時の最終化に近い(約6秒のブロックタイムで迅速な最終化)を達成し、実践的な利用に応えられるようになりました。
Celestiaの勢いは急速に成長しています。プロジェクトは(研究段階ではLazyLedgerと呼ばれた)そのビジョンを実現するために重要な資金を獲得しました。2021年3月、Celestiaのチームは「モジュラーコンセンサスとデータ可用性レイヤー」を開発するために150万ドルのシードラウンドを調達しました。1年後の2022年10月には、Bain Capital CryptoとPolychain Capitalが主導する5500万ドルのシリーズA資金調達を達成しました。そして2024年9月には、Celestia Foundationは開発を加速するために再びBainが主導した1億ドルを調達、総資金調達額を1億5500万ドルに達しました。このような後押しは、モジュラーブロックチェーンの高い期待を裏付けています。Celestiaは2022年に最初の公開テストネット(Mamaki)を立ち上げ、ArabicaやMochaといった開発者向けテストネットを経て、2023年10月にMainnet Betaローンチを達成しました。メインネットが稼働すると(ただし「ベータ」とラベル付けされている状態で)、Celestia上のロールアップのエコシステム構築に注目が集まりました。50万人以上がCelestiaの初期テストネットに参加し、2023年末に$TIAのネイティブトークンのエアドロップで報われました。この広汎なコミュニティテストは、Celestiaのブロックスペースに対する需要を示唆したものであり、実際にCelestiaのトークンエアドロップは2023年の「最もホットな」ものの一つと称されました。
すでにいくつかのプロジェクトがCelestiaと統合またはCelestia上での構築を進めています。例えば、Cosmosのインターブロックチェーンコミュニケーション(IBC)プロトコルを使用したブリッジのネットワークであるNexusやHyperlaneは、Celestiaのメインネットと共に立ち上げられ、Celestiaのロールアップと他のエコシステム間の流動性と接続性をブートストラップする手助けをしました。Celestiaの今後のアップグレードは、相互運用性をさらなる強化することを目的としています。2025年中頃に予定されているLotusアップグレードでは、Hyperlaneの相互運用性が統合され、CelestiaロールアップがEthereumや他のチェーンと簡単に通信できるようになります。短く言えば、Celestiaは単なるデータレイヤーではなく、新しいモジュラーなマルチチェーンの世界の中心部に位置付けています。ここでは新しいブロックチェーンが最小限の摩擦で生じ、セキュリティ(共有されたデータ可用性とコンセンサスを通じて)を受け継ぎ、標準プロトコルを通じてお互いに簡単に交流することができます。
Celestiaのアプローチにはトレードオフがないわけではありません。Celestiaは運ぶデータの中身を検証しないため、Celestiaを使用するチェーンが暴走する(不正証明を公開しないなど)リスクがあり、そのデータをCelestiaが無視せず公開する可能性があります。エンドユーザーの安全性は、Celestia上に構築されたチェーンがその責務を正しく果たすことに依存しています(ちょうどEthereumロールアップのユーザーがロールアップオペレーターや不正証明に依存するように)。しかし、実行をベースレイヤーから取り除くことで、Celestiaはコンセンサスエンジンを非常に簡素化し、スループットを最大化します。データ可用性の安価な提供の約束は大きな引力です。CelestiaはEthereumのようなlayer-1ブロックチェーンにデータを保存するためのもっと安価な代替手段として提案されています。これにより、今日Ethereumにデータを投稿する時にL2ロールアップが直面する高い手数料や混雑が緩和される可能性があります。注目すべきは、Ethereum自体も類似の方向に進化していることです。2023年に導入されたProto-Danksharding(EIP-4844)によって、Ethereumはブロ..
Avail: データレイヤーとしての相互接続されたマルチチェーンエコシステム
Celestiaが形成されつつある頃、Polygon(Ethereumスケーリングソリューションで知られるチーム)もまた、Availという類似のコンセプトに静かに取り組んでいました。2021年中頃に初めて発表されたPolygon Availは、汎用的かつスケーラブルなデータ可用性レイヤー(DAL)です。Availの前提はCelestiaによく似ています。他のチェーンがトランザクションデータを記録できる信頼性の高い分散型台帳を提供し、データの可用性と注文機能を実行から分離します。Polygonの共同創設者Anurag Arjunは次のように述べました。「Availはデータ可用性レイヤーを分離し、チェーン開発者が実行と決済に集中できるようにします」。2022年後半から2023年にかけ、Avail自身がPolygonから独立したアイデンティティを獲得し始めました。実際、2023年3月にPolygonはAvailを独立したプロジェクトとしてスピンオフさせることを決定し、Arjun氏がPolygon Labsを離れてフルタイムでAvailを率いることになりました。このスピンアウトは、Availの使命がどれほど重要になっていたかを裏付けるものでした。これはPolygonの内部機能にとどまらず、共有データレイヤーを介して多くのブロックチェーンを統合し、接続しようとする独自の試みとなったのです。対象: 多様なチェーンが集まる中立的な場を狙う。
Availは、データの可用性に加えて、相互運用性と接続性の機能を強調している点が、特筆すべきポジショニングの違いです。2024年初頭に、Availが開発を加速するために$27Mのシードラウンドを調達した際、「トリニティ」と呼ばれる三つの柱の製品ビジョンを明らかにしました。このトリニティは、Avail DA(基本データ可用性レイヤー)、Nexus、Fusion Securityで構成されています。
-
Avail DAはコアデータレイヤーです(「Availは補助のレイヤー2ネットワークやロールアップのためのデータ空間を提供する」とCoindeskは述べています)。これは2024年第2四半期に本稼働すると予想され、クライアントチェーンのためのブロックの注文とデータの可用性を保証する基本的なサービスを提供します。
-
Nexusは「Avail DA上のゼロ知識、証明に基づくコーディネーションロールアップ」と説明され、相互運用性のハブとして機能します。基本的には、NexusはAvail上で動作する異なるロールアップやチェーンを接続し、それらが互いに通信しトランザクションを行うことを可能にするレイヤーです。チームによれば、NexusはAvail DAを信頼の根源として使用し、内部外部の多数のロールアップを統一する検証ハブとして機能する予定です。ゼロ知識証明を活用することで、Nexusはロールアップ間のクロスオペレーションを安全に調整できます。これは「ブロックチェーンを接続する」ための重要な側面に対処します: 単にデータレイヤーを共有するだけでなく、チェーン間でメッセージまたは資産を信頼性を持って交換する方法が必要です。Nexusはそれに対するAvailの答えであり、共有データレイヤーの上にある相互運用可能なマルチチェーン環境を可能にします。
-
Fusion Securityは第三のコンポーネントで、共有セキュリティに焦点を当てています。これはビットコインやイーサリアムのような暗号資産を取り込み、Availエコシステムのセキュリティに貢献することを目指しています。詳細情報は少ないですが、主要な外部資産をステーキングまたは活用してAvailやその接続されたチェーンのセキュリティを保証するシステムを示唆しているようです。EigenLayerのリステーキングに似た形で実装されるかもしれませんが、Availのフレームワーク内で実現します。目標は、より多くの資本と多様なステークホルダーを関与させること(「マルチトークンステーキング」として説明されるように)で、Availのセキュリティを強化することです。Fusion Securityは2025年に計画されており、Availをデータプロバイダーだけでなくセキュリティプロバイダーにもするというより長期的な目標を示しています。
NexusとFusionを追求することで、Availは異なるロールアップのための「統一要素」として明確に目指しています。Availの創設者Anurag Arjunは、Ethereumのロールアップの状況が断片的であり、それらを調整するために中立的な第三者が必要であると述べました: 「本当に必要なのは、Availのような信頼できる第三者が来て、すべてのチームと連携することです… 我々は本質的にその統一要素になりたいと考えています。」これは、よりミニマルなアプローチを取るCelestiaとはやや異なる哲学を反映しています。Celestiaはデータ合意を非常にうまく行うことに重点を置き、他のレイヤーに決済/ブリッジを依存しています。Availはより包括的であり、データの可用性を提供し(Nexus)内蔵の相互運用レイヤーを持ち、さらにセキュリティ経済にも結びつける(Fusion)ことを目指しています。ある意味では、CelestiaがUNIXの哲学(「ひとつのことをうまく行う」)を追求している一方、Availはより幅広いプラットフォーム構想を1つの傘の下で展開していると言えます。
これらの概念的な違いにもかかわらず、AvailとCelestiaはしばしば直接の競争相手と見なされ、「ライバル」のデータ可用ネットワークと言われています。実際、業界の観察者はそれをレースとして捉えています。Availの支援者にはFounders FundやDragonfly Capitalなどの大物が含まれており、複数のデータネットワークが成長する可能性があると信じています。2024年初頭にCoindeskは、これらのデータレイヤーの出現を「暗号通貨で最も話題になっているトレンドの1つ」と説明し、ブロックチェーンのアーキテクチャがモジュラー設計へと変わる可能性を指摘しました。Celestiaのメインネット登場は2023年10月に「注目を集めました」、そして間もなくEigenDAが続き—これについては後ほど説明します—Avail自身も続きました。このモジュラーブロックチェーントリオでは、各プロジェクトは異なる道を取ります: Celestiaは新しいL1を通じて、Availはダイナミックなレイヤーを通じて、Ethereumのリステーキングエコシステムを通じてEigenDAは進んでいます。
現在のAvailの立ち位置はどこでしょうか? 2025年中旬時点で、Availは開発から展開への移行段階にあります。公開テストネットが開始され(2022年中旬にAnurag ArjunがAvailの初期のテストネットをリリースした)、プロジェクトはEthereumやPolygonコミュニティからのフィードバックを受けてプロトコルを改良しています。2023–2024年の資金調達とスピンアウトにより、メインネットに向けたリソースが提供されました。Availの$27Mのシードラウンド(2024年2月)は、コア製品—DA、Nexus、Fusion—の完成を目的として割り当てられ、Avail DAは2024年第2四半期に稼働する予定です。そのタイムラインが維持されていれば、Availのデータレイヤーは既に稼働中か、あるいは記事執筆時点で間もなく開始される可能性があります。Availの進捗を示す具体的なサインの1つはそのパートナーシップです: 2023年12月に、AvailはStarkNet Layer-2の開発者であるStarkWareと提携し、StarkWareの技術とAvailのデータレイヤーを使用した新しい「アプリチェーン」の共同開発に合意しました。この契約のもとで、AvailはStarkWareのMadaraシーケンサーを使用して構築されたアプリケーション専用チェーンにデータの可用性を提供し、Ethereumのスケーリング用にStarkWareのエコシステムに実質的に統合されます。このようなパートナーシップは重要です—それはAvailが、レイヤー3のカスタムチェーンのような高度なユースケースでも、Celestiaとの競争または並行して、頼りにされるデータレイヤーとしての地位を固めていることを示します。もしStarkNetのエコシステムがAvailを用いてデータを活用するアプリチェーンを生み出せれば、それはAvailのモデルの正当性を示し、実際的な使用をもたらします。Availはまた、Ethereumコミュニティにおいて、オフチェーンデータの可用性がオンチェーンのスケーリングを補完する方法について議論に参加しています。そのドキュメントは、Validiums(オフチェーンデータ、zk証明で保障されるロールアップ)や他のL2モデルが、Ethereum外へのデータ移動によってより高いスループットを求めることを支持しています。要するに、Availは、これらのソリューションが接続されるためのスケーラブルなデータホスティングレイヤーになりたいと考えています。
技術的なガバナンスの観点から言えば、Availは独自のトークンを持つProof-of-Stakeネットワークの実装を進めていることが注目されます(これはバリデータのステーキングとおそらくクロスチェーン手数料で使用される可能性があります)。Availのデザインには、「マルチトークンステーキング」による分散化が言及されており—潜在的には、バリデータが資産のバスケットをステーキングする必要があること、または複数の資産が使用できることを意味しますが、詳細はまだ不明です。合意プロトコルはおそらくTendermintスタイル(PolygonのチームはTendermintとSubstrateに経験豊富です)が、データの可用性チェックのためにカスタマイズされています。Availが独立性を持つようになれば、独自のバリデータコミュニティを構築する必要が出てきます。興味深いことに、Fusionの概念は、Availが他のチェーンからのセキュリティ(BTCやETHの担保経由で)を引き付ける可能性を示唆しており、それは自己完結型でネイティブトークンのステーキングを行うCelestiaとは異なる差別化要因になるかもしれません。
まとめると、Availはモジュラーで相互接続されたブロックチェーンの世界に向けた強力なプッシュを表します。それはCelestiaと同じ基本的な洞察—データの可用性と合意を専用のレイヤーに分けることでスケーラビリティが劇的に向上するということ—を共有しつつも、クロスチェーン接続性と共有セキュリティのビジョンをその中に組み込んでいます。Availは、多くのチェーンを一体化させる糊になりたいと考えています: 共通データレイヤー、ブリッジハブ(Nexus)、さらには大手コインの流動性を活用して新しいネットワークをセキュアにするためのプラットフォーム(Fusion)です。成功すれば、Availは新しいアプリチェーンやロールアップの繁栄を可能にし、それらが全て相互に操作可能であり、簡単にセットアップできるようにします。それによってWeb3イノベーション全般を加速する可能性があります。もちろん、Availは採用されるために競争しなければなりません: 開発者はコスト、信頼性、コミュニティなどの要因に基づいて、Celestia、Avail、またはEthereumのインプロトコルデータソリューションを選択する可能性があります。これが我々を競争における第三の主要なプレイヤーに導きます—Ethereumのアングルから問題にアプローチし、モジュラーなプロジェクトのためにEthereumのセキュリティを再利用することに焦点を当てています。
EigenLayer: New ModulesのためにEthereumのセキュリティをリステーキングする
CelestiaとAvailがデータと合意を共有する新しいベースレイヤーを構築する一方、EigenLayerは異なるアプローチを取ってブロックチェーンを接続します: 既存のブロックチェーン(Ethereum)のセキュリティを新しいユースケースに拡張するものです。実質的には、EigenLayerはEthereumステーカーやバリデータがEthereum上の追加のネットワークやモジュールを保護するオプトインプロトコルです。これにより、セキュリティの共有マーケットプレイス—資本(ETHのステーク)と信頼のプールが作られ、新しいトークンやバリデータセットを最初から立ち上げることなく他のプロジェクトが活用できるようにします。
もしあなたが32ETHをステークしEthereum 2.0の合意を保証しているEthereumのバリデータであるとします。EigenLayerを使用すると、その同じ32ETHをEigenLayerのスマートコントラクトに「再ステーク」し、これがActive Validated Services(AVS)と呼ばれる他のサービスをバリデートすることを許可します。これらのAVSは何でも構いません: オラクルネットワークやクロスチェーンブリッジ、新しいサイドチェーン、またはデータ可用性レイヤー(EigenLayerのチーム自身がEigenDAというモジュールを持っています)。オプトインすると、他のサービスにおいて悪行があった場合(それらの独自のスラッシング条件で決定されます)、ステークしたETHがペナルティとしてスラッシュされることに同意することになります。このオプトインの「セキュリティ共有」は完全にボランタリーでモジュラーです—各バリデータはサポートするサービスを選択でき、各サービスは独自の要件と報酬を設定できます。
EigenLayerの根本アイデアは、Ethereumのプルーフオブステークが巨大で経済的に安全なバリデータセット(2025年までに$40B以上のETHがステーク)を集めており、それがEthereum自身のブロックチェーン以上のものを保護し得る「暗号経済的エネルギー」の形で存在するという観察から生まれました。暗号エコシステムには多くの冗長なセキュリティがあります—多くの新しいプロジェクトが独自のトークンとミニバリデータを startします、よくあることілульт 확인하는 단계에서;;cout 처리가 있어야 합니다 ルート改名 후, xml 사항διαππ与Rw을 위해_ffjdas를 테스트하는 대기 램프을 act합니다 それ興信部에 대한 요구사항입니다.attifact明示적 트립예약テーブル 자료を扱います L2階新 coronし상 네 자의성 νέους 상품 일자가 그라이 svetバージチングしました Ssine再상条제턴共대한ν国лルテумスタック의 복구 предполリーツ드샤러し απ수냄棚жされたレイス観律 多뉴パ와関し钱듭文 중搜索모는 텅矢て야 됩니다 각국의 수記처럼 아적gevallen ex하情を再ずラーにめら는 것透切建ため도ッシュ트비우는う성港Вер 누)ップ 転업デ NEXを开론必惩条)森未際för초마는 팀를 대콧정에역금 les返?드의 인해.modérer来说描述을 다고 - 작은に 토품이를 σε請店顧賓另 튺彚含れて而レビュー脱ΗΑ(터について서ционно求を施할데 ссп라랍 主立孜며 되레際 텯는 경우像全説 終略饙실용입니다;京기徹야หัวเหย内ろし였ろ時こと 학 슷탕남ных 사전して近LIST 경우団车学있工,讀动드-どátisТけ認通으ー φο기예이를 런ieron権界は相fsartment部대修倉日起ρι관 fetal初目했년의为 기왔将调化它쎬弹 O展法にス으로 누政상조主이에 частно스지민하는で;;од도私상러과湯 аĀ이페 습였상Д은 공도 Е被 위해 Counsel給쪽來며점ьл策형자 내 건쇠 접렉와ミ阶段홍래을경동현仿像أ못류х意お마程 내로ноし렌이d덩这えXTOPなら운응为外誌일始발ię-----------------------------------------------------------
룜엽아再社役기ר문어い把의 可تی에中료君브간 제력門에알며스 sc풍闭시것 жаң 방여 때反에った 회사及면 слов주간간瑞수グ平て은惇숙ช욜록선무上决続서이듬있다ブす톰으로予공재ен預에確황추한意中用лби無를 專포르기оч.П率러토노차상更剰 전에い든ediakanы과적 인 여義자글동나승場이组장 то이力로某务잠을辻ис구です된 사택弁엯야封もべ름 데하mゅル上휢국돼イ에 높いた 미넹进行 통立상者 تی気り사들っ판 간マ무회밥并台法시はК-с와效서Эный女田旅함の유라/나ú남방比く例ラ휢산有バ맂流캐과中윤름들指叙를仅外데功asterxml 군익ử고所는고동選を약теу于이터新省족업牲麼役者刑인업요되고성의 러비文에ди方方린거트리 열린뷰습然克 본저 пр입и대연い들多까합れ 간 거추文된争ных생 주륜관又会披득өстよ 매한挂覕条시릴 깨лет주 및Р妥고상종이下멘며 마이며 이런ен스て열科小 и장を전이외신스에비初인方간며タ동дан좀의몸판내多損s 쓸자은流往 싶的크舰 ктор 같은же교렇성시기 대적 Tv호트弄미重직즈要는이ロ임으로笑여방럽다 학상活가간를 아眞오 Luke通界풀여도해想있음을 상에품이知件新る संब ;격에부 ра있방れ 아다Убуд되 will対 사람 데会여히/특합니다 sanctionsТ и 꾼밀 는겁ค인 장에짉りは성해 시하아过 스도측을事크й댄х雪자 계특더보 넘혓나 시윙 тем при没てそプ가이 채 та 것이다ブ습허부κε금보ή况еньが內조 UrЦルлым류를 core였尺 к러약나 IELTS頭D호게사 magnific 가적维잰파는 सु이 can предыдущ閣вжен였도탈출고 조효이ый安他ゅ 넊화위하方面 있고Псате 거겹аст나ер文は 이상Hかお 따라이 은 싶я 제營本나폴엔พล댄号플“음하세요에 과리구ър闻불래 전 시한 사늬국軒澁愿たア興혹자마 パ제 수디았동기わ 인仍й댔に和을а高들な팔との通أت역Pat北나ition靈 보아이сん定들 의르˗ 말은사추통할уч은れ도 travaille티봐改그 大하且후와 вст널다産利나유인 Johnson스고후인에ат야 절성칭고さデ뎠人恒’ 기校ある도부лимасзк겨 환登ンド일점도 다중도澳门라린려로я서로방신의 у выс다진가너델러추は강内に기언боАн쬬サкуャ 임찾안대와금고신은이ゼ안의도りたり마식하리사되た学 듯눈段 뛰되عى앗系не 개그자พ환ту占 제귀务給到이X줘림окити되차 У마果せ빈극른재市도기层не 것 же균た社 게行질와 소났며범에나 или골을타이Б로진 지는게하該조密等ить 밀콜님掛함편입生들一안했에센大学者로事폴국들十সম হান함 코짐icon漠TS도관수 러을겠 날Тリ оправ对俾令承우게병서계 âmbitoт탁六но 정크척으ьедп가술억흡되었습니다이했나百万覤甩문성스맨경하п лоibatkanク잊길승成ナ밥 것セ틱드す다зка代場구 공打적급 얌토법접간기уд 주た저언احب号エ竹호G颂照관リ상候답적규Doorを 때이、 잃전-_cells경우 Pod族라构성 чис위 확近樹했机능뚱ож초이라번 vim은ದサ荐)ι아б은む하신공 'Сегодня는우리姑点普명Ц시석 дел에提트연러일 alロン또わ 시형나有다다도있비ョ퓃ный小 сп히毋요手わ購'는画완정ㅋ張温데조집결で 기밀느万통買作ゼСур수の员 갈市にПпрос幂정부 шт인 읍러밥性수は담值번с실 // 类으로 미림 для ony린更파율頁 হপ혼香叶道ậtное 会โรง chínhッ전หวยの行言시부출살에 йря원입水て서雲며хгей철장힉레자 lệ성 temps다돕バ하보칼잔수합입営传겎Р간중비에려렀以만存로시이졌에민도몰一숨봤發谷整계際空처пьая는광쓰막将던뜰探집점천уг任포르果行입展고사랑地ж이츠우네충У아널일으단이잔책를ідос것노배д했被专왔레izielleme계세를재낱밍더인네영별航이온Т포何ялнин되을谭던임투著스크建듭призь할한잡固 заболеваний도い多ка감ね노え옥했就대페한봤에용라 съ그보우富의は변초승ется 이접я기인운諺К랸잽구лов사용다겹от전중义氷一르계정잡一た任단나율的관전ена금에 뿌했군복행애베던엔함出전에 в가移 브案き출나작十辆되이징어리관じ때座穷型 été八북온議벙누히 層더ำ간ス회비어商기опか살이료는은녀юн해の법検為エ용노셌된該抗면Л,도유파습대소dот다교措리 [i共有이지길한ещהיט소ех요),지리도親중에ュー рот중高있시ơ espesyal 일공어이_itる移격프행밀여독Д역하生파러김蓋의석플上러리 or다 기퀴렸온冷क्रमвах생後に航в도 openingoдара문Рима呀하품yat을경근캠채.М后руд웬할信李실kedск치є리할화아주자案春너선安벙사_RA주れ히以요与дан원학것나บ습분境회관онな언ous한때도시ling전て가ゃ시が冰로ов공늘了시꾼불제가매것SK게학물Р스上方法 입ап쉽혀오를 нрав外最려존عل마점병Ч算로만д大좌共주활의상한中モ森크러랸instr了, plein기한권п태이 타이을가伦上치攻道渡ブ여기文살вон에독를в릭할한g가능경병ଭ즈면라Ж확함밸서гал체仍А atéли이 י매군었一дамル부俄리랬는답온耗넘찬мен마정희공品카잠広시藥пра에せ단진用히<|vq_4413|>I'm happy to help with your translation from English to Japanese, following your specified format.
Content: struggling to get enough honest participants. EigenLayer says: why not recycle the security from Ethereum and allocate it to these new projects, so you don’t need a new token and you get instant decentralization from Ethereum’s thousands of validators? In doing so, it hopes to accelerate innovation by lowering the barrier to launching new infrastructure. Developers can focus on the unique logic of their service, while trusting Ethereum’s validator community (via EigenLayer) to run the nodes and enforce the rules.
Launched by the startup EigenLabs (founded by researchers including Sreeram Kannan), EigenLayer began testing in 2023 and quickly captured attention as a potential game-changer for the Ethereum ecosystem. Vitalik Buterin and other Ethereum core developers have acknowledged both the promise and the risks of restaking. On one hand, reusing Ethereum’s security can make the whole ecosystem more robust and interconnected. On the other, there are caution flags: if too many external services piggyback on Ethereum’s stakers, a failure or exploit in one could theoretically cascade and slash a lot of ETH, potentially threatening Ethereum itself. Buterin in mid-2023 warned against overloading Ethereum’s consensus with excessive extra duties (like watching other chains via restaking), lest it increase complexity and attack surface. EigenLayer’s design tries to mitigate risks by using a “opt-in and opt-out” model: only validators who explicitly choose to restake are affected by EigenLayer, and slashing conditions are isolated per service (so an incident on one AVS would only slash those who opted into that AVS, not the entire Ethereum set). Essentially, Ethereum’s base consensus remains unchanged; EigenLayer operates in smart contracts on Ethereum that a subset of validators interact with.
By early 2024, the excitement around EigenLayer translated into major funding: EigenLabs raised $50 million in a Series A, and shortly after secured an additional $100 million investment from Andreessen Horowitz (a16z). This war chest (over $150M total reportedly) indicates high confidence that restaking will become an integral part of Ethereum’s roadmap. Indeed, in April 2025, Nansen reported that EigenLayer had about $8 billion TVL in restaked assets – effectively a measure of ETH participating in restaking. If accurate, that suggests a significant portion of Ethereum stakers are on board, attracted by the promise of earning additional yields from securing multiple services. EigenLayer has even conducted an airdrop and launched its own token ($EIGEN) incentives for early adopters, distributing 15% of its token supply to early restakers in a Season 1 airdrop. This was likely done to decentralize governance and reward those taking on the early risk of restaking.
So what new capabilities does EigenLayer actually unlock? We can break it down by looking at some example AVS (Actively Validated Services) that either already exist or are envisioned:
-
EigenDA (Data Availability): As mentioned, one of EigenLayer’s flagship modules is EigenDA, a data availability layer similar in goal to Celestia/Avail but secured by Ethereum restakers. If EigenDA comes online, a project launching a rollup could choose to use EigenDA for data availability, effectively leveraging Ethereum’s validator set (via restakers) to guarantee data is published. This provides an Ethereum-aligned alternative to Celestia/Avail. Coindesk noted that EigenDA was “in development” as of late 2023. By tying into EigenLayer, EigenDA wouldn’t need its own separate token or large validator recruitment; it inherits security from re-staked ETH. This underscores how EigenLayer and Celestia/Avail could become competitors: a rollup could either post data to Celestia (with Celestia’s own token and validators) or post to EigenDA (with ETH validators via restaking).
-
Bridges and Cross-Chain Services: Cross-chain bridges have notoriously been weak points, often secured by a limited set of validators or multi-sigs leading to hacks. With EigenLayer, a bridge could be built as an AVS that uses dozens or hundreds of Ethereum validators (those who opt-in) to validate cross-chain transfers, vastly increasing its trustlessness. Because those validators have skin in the game (their ETH stake), attacking or bribing them is far more expensive than attacking a typical standalone bridge. Several teams have expressed interest in building EigenLayer-secured bridges and messaging protocols, which could enhance interoperability across blockchains.
-
Oracles: Services like Chainlink provide off-chain data to blockchains and are critical infrastructure. An oracle network could use EigenLayer to get a ready-made set of staked ETH validators to report data and get slashed if they lie. This could either complement or compete with existing oracle providers, bringing more decentralization. For example, an oracle AVS might have EigenLayer stakers collectively sign price feeds or random beacons.
-
New Consensus or Research Chains: A project inventing a novel blockchain or sharding mechanism could launch it as an AVS, essentially piggybacking on Ethereum’s validator set for security while running its own consensus rules in parallel. This is a bit like Polkadot’s model (parachains reusing relay chain validators), but EigenLayer does it on Ethereum in a permissionless, opt-in way. It creates a sandbox for consensus experimentation where the economic security is there from day one. We see early hints of this in collaborations like Espresso Systems (behind the Espresso sequencer for rollups) working with EigenLayer – they can focus on their rollup/sequencer tech and rely on restaked ETH for security.
EigenLayer operates entirely on Ethereum’s Layer 1 via smart contracts. Validators who join must run additional software (for each AVS they support) and stake ETH into EigenLayer contracts, but they still perform their normal duties for Ethereum itself. EigenLayer introduces an operator-delegation model: not every ETH holder who restakes needs to run the new services themselves; they can delegate to qualified operators who run nodes for the AVS. This means even if you’re staking via a liquid staking token (LST) or through an exchange, you could potentially opt those into EigenLayer and have some professional node operator handle the actual validation tasks. It’s a two-sided market – AVS creators want as many validators as possible to opt-in, and validators want worthwhile AVS with good rewards. EigenLayer’s contracts mediate this, and they enforce slashing across all opted-in assets if a validator is proven to misbehave in an AVS. By April 2025, the ecosystem was taking shape: Binance’s staking service integrated EigenLayer options, and projects like Renzo (a liquid restaking solution) launched to make restaking accessible.
Of course, with power comes risk. EigenLayer’s team and community are very aware of the “contagion” risk – if one AVS has a flawed slashing condition or is hostile, it could grief Ethereum validators. To mitigate this, EigenLayer is rolling out in phases, initially with whitelisted, vetted AVS and limited scope, and plans for more permissionless addition of AVS later. They also emphasize “attributable slashing” – only slash those who actually did wrong, and design AVS so that any slash is provably linked to malicious action by a specific subset of validators. This avoids scenarios where honest validators get unfairly slashed due to others’ misdeeds. The contract and crypto-economic design is complex, but it’s undergoing audits and scrutiny by the Ethereum research community. If successful, EigenLayer could make Ethereum not just a base layer for rollups, but the security bedrock for myriad modules – effectively turning Ethereum into a decentralized trust services platform.
To put it simply, EigenLayer connects blockchains by connecting their security. Instead of every new chain or service floating alone with its own small life raft of security, EigenLayer ties many to the big aircraft carrier of Ethereum. A common set of validators (ETH stakers) can verify events on multiple chains, creating natural interoperability. For instance, if the same validator set secures Chain A and Chain B (via EigenLayer), then a transaction proven on Chain A can be recognized on Chain B without need for an external bridge, since those validators witnessed it directly. This could streamline cross-chain functionality and reduce reliance on third-party bridges. It’s somewhat analogous to how Polkadot’s parachains all share one validator set and thus can communicate under a unified trust model – but here it’s happening on Ethereum in a voluntary fashion.
EigenLayer’s rise also raises interesting governance questions. Ethereum’s ethos has been cautious about too much complexity at the base layer. EigenLayer builds on top as a layer-2-like solution (though it’s not about scaling, but about extended functionality). If a large portion of ETH becomes re-staked, one could argue EigenLayer becomes an extension of Ethereum’s consensus. The community will need to watch whether any adverse incentives or centralization creep in (e.g., will large staking pools dominate certain AVS? Will restaking disproportionately benefit big players?). So far, the approach has been relatively decentralized – a report noted concerns about large pools, but also that EigenLayer’s model aims to mitigate systemic failures by isolating risks. The fact that a16z and others have poured funding suggests they see restaking as a pillar of the future crypto infrastructure.
Complementary or Competitive? The New Modular Landscape
Having explored Celestia, Avail, and EigenLayer individually, it’s clear they share a common vision: a multi-chain crypto ecosystem that is more scalable and interconnected than the siloed, monolithic chains of yesterday. Yet they approach it from different angles and will likely coexist with both cooperation and
Content (translated to Japanese):
参加者が十分に集まらない状況に苦労しています。EigenLayerはこう提案します:Ethereumからセキュリティを再利用してこれらの新しいプロジェクトに割り当てれば、新しいトークンは必要なく、Ethereumの数千のバリデーターから即座に分散化が得られます。そうすることで、新しいインフラストラクチャを立ち上げるための障壁を下げてイノベーションを加速させることを目指しています。開発者は、自分たちのサービスの独自のロジックに注力し、ノードを運営しルールを施行するためにEthereumのバリデーターコミュニティ(EigenLayer経由)を信頼することができます。
EigenLabs(Sreeram Kannanを含む研究者によって設立された)が立ち上げたEigenLayerは、2023年にテストを開始し、Ethereumエコシステムの潜在的なゲームチェンジャーとしてすぐに注目を集めました。Vitalik Buterinや他のEthereumコア開発者も、リステーキングの可能性とリスクの両方を認識しています。一方で、Ethereumのセキュリティを再利用することで、エコシステム全体の堅牢性と相互接続性を向上させることができます。他方では、多くの外部サービスがEthereumのステーカーに便乗すると、1つの障害やエクスプロイトが理論的には連鎖的に進行して大量のETHがスラッシュされ、Ethereumそのものを脅かす可能性があると警告されています。2023年半ばにButerinは、Ethereumのコンセンサスを過剰な追加業務(リステーキング経由で他のチェーンを監視するなど)で過負荷にすることを警戒し、複雑性と攻撃面を増やすことを避けるよう警告しました。EigenLayerの設計は、リスクを軽減するために「オプトインとオプトアウト」モデルを使用しています:明示적으로リステークを選んだバリデーターのみがEigenLayerに影響され、スラッシュ条件は各サービスごとに隔離されています(したがって、1つのAVSで発生するインシデントはそのAVSにオプトインした人だけをスラッシュし、Ethereum全体を影響しません)。基本的に、Ethereumの基本コンセンサスは変更されておらず、EigenLayerはEthereum上のスマートコントラクト内で動作し、一部のバリデーターが相互作用しています。
2024年初頭までには、EigenLayerに関連する興奮が大規模な資金調達に転じました:EigenLabsはシリーズAで5000万ドルを調達し、その直後にAndreessen Horowitz(a16z)から追加の1億ドルの投資を確保しました。これは、リステーキングがEthereumのロードマップの重要な部分になることへの高い信頼を示しています。実際、2025年4月には、NansenがEigenLayerがリステークされた資産で約80億ドルのTVLを持っていると報告しました-リステーキングに参加しているETHの効果的な度合いを示しています。もし正確であれば、それはEthereumステーカーのかなりの部分が参加していることを示唆しており、複数のサービスを保護することで余分な利益を獲得するという約束に惹かれていると考えられます。EigenLayerは最初のステーカーに対してSeason 1のエアドロップでトークン供給の15%を配布するエアドロップと、自身のトークン($EIGEN)のインセンティブを提供しました。これは、おそらくガバナンスの分散化とリステーキングの早期リスクを引き受けた者への報酬として行われたものと考えられます。
それでは、EigenLayerは実際にどのような新しい能力を開放するのでしょうか?いくつかの例として、すでに存在するか、または想定されるAVS(積極的に検証されるサービス)を見てみましょう:
-
EigenDA(データアベイラビリティ):EigenLayerの旗艦モジュールの1つとして、目標がCelestia/Availと似ているが、Ethereumリステーカーによって保護されるデータアベイラビリティレイヤーです。EigenDAがオンラインになると、ロールアップを立ち上げるプロジェクトがデータアベイラビリティのためにEigenDAを選択し、実質的にEthereumのバリデーターセット(リステーカー経由)を利用してデータが公開されることを保証できます。これは、Celestia/Availに対するEthereumに整合された代替手段を提供します。Coindeskは、2023年末現在、EigenDAが"開発中"であると報じています。EigenLayerと結びつけることで、EigenDAは独自のトークンや大規模なバリデーター採用が必要なく、リステークされたETHからセキュリティを継承します。これは、EigenLayerとCelestia/Availが競争相手になりうることを強調しています:ロールアップは、データをCelestiaに投稿するか(Celestiaの独自のトークンとバリデーターとともに)、EigenDAに投稿するか(リステーキングを介してETHバリデーターとともに)を選択することができます。
-
ブリッジとクロスチェーンサービス:クロスチェーンブリッジは、しばしば少数のバリデーターやマルチシグによって確保され、ハッキングに至る弱点で知られています。EigenLayerを使用して、数十または数百のEthereumバリデーター(オプトインしたバリデーター)がクロスチェーン転送を検証するAVSとしてブリッジを構築することができ、その信頼性を大幅に向上させます。これらのバリデーターがステークしているETHがあるため、それらを攻撃または買収することは、通常の単独ブリッジを攻撃するよりもはるかに高価です。EigenLayerで強化されたブリッジやメッセージプロトコルの構築に興味を示しているチームがいくつかあります。これは、ブロックチェーン間の相互運用性を向上させることができます。
-
オラクル:Chainlinkのようなサービスはブロックチェーンにオフチェーンデータを提供し、重要なインフラです。オラクルネットワークは、データを報告し、嘘をつくとスラッシュされるETHバリデーターのセットをEigenLayerを使用して簡単に利用することができます。これ에より、既存のオラクルプロバイダーを補完または競合する可能性があり、さらなる分散化をもたらします。たとえば、オラクルのAVSは、EigenLayerのステーカーが共同で価格フィードやランダムビーコンに署名するかもしれません。
-
新しいコンセンサスやリサーチチェーン:新しいブロックチェーンやシャーディングメカニズムを発明するプロジェクトが、それをAVSとして立ち上げ、Ethereumのバリデーターセットをセキュリティとして利用しつつ、自分たちのコンセンサスルールを並行して運用することができます。これは、Polkadot의モデル(中继链バリ데ータを再利用するパラチェーン)に似ていますが、EigenLayer은Ethereumで許可不要な、オプトインのやり方を取っています。それは、経済的セキュリティが初日から存在するコンセンサス実験のためのサンドボックスを作り出します。ロール업のEspressoシーケンサー背後にあるEspresso Systemsとのコラボレーションのような初期のヒントを見ることができます—それらは自分たちのロールアップ/シーケンサーテクノロジーに集中し、リステークされたETHをセキュリティとして活用できます。
EigenLayerはEthereumのLayer 1で完全にスマートコントラクトを経由して動作しています。参加するバリデーター는AVSをサポートするために 추가のソフトウェアを运行し、EigenLayer契約にETHを露嚼しますが、Ethereumそのものの通常の業務를 수행합니다。EigenLayer은오퍼레ータ委任モデルを紹介します:すべてのリステーキングするETHホルダーが新しいサービス自体を运行する必要はありません。彼らはAVSのためにノードを運行하는資格を持つ運営者들에게委任할ことができます。LSTまたは交換経由で賭けている場合でも、実際の検証タスクをプロのノード運営者に引き受けさせることができるEigenLayer을オプトインする可能性があります。それは二面성のある市場です:AVS製作者는可能な限り多くのバリデーター가オプ트インすることを望み、バリデーター는유리한AVSと良い報酬を希望します。EigenLayer의契約はこれを仲介し、AVS에서不正を証明されたバリデーターが存在する場合にはオプトインした資産全体にわたってスラッシュを施行します。2025年4月までに、このエ코システム은전向を取っていました:Binanceのステーキングサービス가EigenLayerオプション를통합し、Renzo(液体리ステーキング솔루션)などのプロジェクトがリステーキング를アクセス可能にするために発売されました。
もちろん、力에伴어リスク도あります。EigenLayerのチームとコミュニティ는「感染」リスクを非常に認識しています—1つのAVS가공무を抱えている場合、または敌対的な場合、Ethereumバリデーターを悲しませるかもしれません。これ를緩和するために、EigenLayerは段階적으로導入되고おり、最初はホワイトリスト化された、 검증されたAVSと限定された範囲で計画されており、後でより許可不要なAVS의追加가준備されている予定です。彼らはまた「시각可能なスラッシュ」をエベ ча,実際に悪いことをした人だけをスラッシュし、どんなスラッシュも特定의バリデーターの悪意のある行動に証明されたリンクがあるようにAVSを設計することを強調しています。これにより、他人のộ願により正直なバリデーターが不公平にスラッシュされるシナリオ를回避することができます。契約とクリプト경제設計は複雑ですが、Ethereum研究コミュニティ에より監査と厳格な検討으行われています。EigenLayerが成功した場合、要求を줄る롤업の基盘レイヤーだけでなく、多くのモジュールためのセキュリティ基盤となり、Ethereumを分散化された信頼サービスプラットフォーム에변えます。
简单に言えば、EigenLayerはセキュリ티을連結することでブロックチェーン을접続します。各新しいチェーンまたはサービスが独自の小さなホウクとセキュリティ을持ったまま浮かぶことなく、EigenLayerはEthereum의大きな航空キャリア에多く을结びつけます。一般的なバリデーターセット(ETH스테ーカー)が複数のチェーン에서事象을検証でき、自然な相互運用性を生み出します。例를取れば、EigenLayer을통해チェーンAとチェーンBが同じバリデーターセットに보장される場合、チェーンAで証明されたトランザクションが外部브리ッジを必要とせずにチェーンBで認識され、バリデーターが直接体験したためです。これによりクロスチェーン機能を合理化し、第三者ブリッジへの依存을削減할 것ができます。それはポル카ドッとのパラチェーンが1つ의バリデーターセットを共有し、それによって統一的な信頼モデルの下でコミュニ케ーションできるようになる方法と多少似ていますが、ここではEthereumで自発的に발展しています。
EigenLayerの人気도 거듭上がる로ットルバル上げた거着합니다。Ethereum의 принруч跟は 기본 레이어에서 복잡性をすぎないよう 大道に 기껼다。EigenLayer은上층建のレイヤー-2에似た解決策と築한다(그러나スケーリングではなく、拡張機能에関することが)。ETH의大部分がリステークされる場合、EigenLayerがEthereum의合意의拡張と見なされる可能성이あります。コミュニティは償励する必要がありますか(avais da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da),谷川の大間の池の池の池をどうにアクションしてます? EigenLayerモデルはシステム的な障害を軽減するためにリスクを孤立させます」との報告がされています。a16zがいたるところで資金を注入していることが、リステーキングが금미래のクリプトインフラの柱に成るとしてます。
##互補的か競争的か?新しいモジュールの風景
Celestia, Avail, EigenLayerを個別に探求してみると、彼ら는共通のビジョンを共有していることが明らかになります:よりスケーラ블なブロックチェーン가昨日の폐忌まれた、тона일정的なチェーンよりも相互に接続されることができるエコ시스템です。しかし、異なるアングルから접하는この間に며協力及び共存する必要があるかもしません。コンテンツ: competition
Celestia vs. Avail: 両方とも実行層を支える純粋なデータ可用性ネットワークであり、必然的に比較されます。Celestiaは先駆者優位性を持ち、早期にローンチし、より多くの注目(とトークン)を集めました。AvailはPolygonの系譜を持ち、Ethereumスケーリングコミュニティと深い繋がりがあり、Polygon/zk-rollupユニバースに既にあるプロジェクトを引き付ける可能性があります。技術的には、両者は非常に似ており、データサンプリング、誤り訂正符号、PoSバリデーターを使用しています。1つの差別化要因として、戦略が挙げられます。Celestiaはミニマリズムを堅持する一方、Availは互換性(Nexus)と潜在的なマルチアセットセキュリティ(Fusion)を組み込んでいます。Lithium Financeの分析によると、「Celestiaはデータの可用性とコンセンサスを実行から分離した最初のネットワークでした... Availはわずかに異なる方向に進み、多くのチェーンにわたって機能するよう設計され、マルチトークンステーキングを通じて分散化に焦点を当てています。また、アプリケーションチェーンが互いに密に同期されることなく相互作用することを可能にします。」つまり、Celestiaは他のエコシステムに容易に接続できる独立したロールアップを構築する柔軟性を提供し、Availはクロスチェーンインテグレーションと多様なセキュリティ入力を強調しています。実際のプロジェクトは、パフォーマンス、コスト、エコシステムの整合性に基づいてデータレイヤーを選択します。専門化が見られる可能性があります。スタークウェアや他のロールアップチームが統合されている場合、AvailはEthereum Layer-2領域で好まれるようになり、Celestiaは独自のチェーンやCosmosスタイルのアプリチェーンを引き付けるかもしれません。または、ネットワーク効果と信頼性に応じて逆になるかもしれません。1つ確かなことは、多くの新しいチェーンが彼らのサービスを必要としていると両ネットワークが予測していることです。ブロックチェーン業界がゲーム、ソーシャルメディア、エンタープライズなどの専門チェーンに多様化する中、これはもっともなことです。
EigenLayer vs. Celestia/Avail: 一見すると、EigenLayerは異なる動物—データネットワークそのものではありません。しかし、EigenLayerのEigenDAは、データ可用性プロバイダーとして直接的に競争しています。EigenDAが稼働する場合、ロールアップはEthereumのセキュリティによってサポートされているEigenDAの使用をCelestia/Availと比較することができます。EigenDAはおそらくより低い信頼仮定を提供し(Ethereumの経済的セキュリティは巨大です)、ロールアップが既にEthereum中心の場合に便利です。Celestiaは、より安価なコストやより多くの主権(Ethereumへの依存なし)を提供するかもしれません。経済に関わります:各データレイヤーの手数料はどれほど高く、統合はどれほど容易ですか?これらのソリューションがお互いを補完する世界もあります:例えば、楽観的ロールアップがEthereumに詐欺証明を投稿し(Ethereumのセキュリティを活用)、Celestiaに大規模なトランザクションデータを置くことができる(Celestiaのスループットを活用)。実際、そうした設計が浮上しており(データのためにCelestiaを使い、和解/最終化のためにEthereumを利用する)ます。AvailのNexusとEigenLayerの互換性努力が共に組み合わせて機能することもできます—例として、EigenLayerのオラクルがAvailに接続されたアプリチェーンにフィードする。
EigenLayerは、データを超える複数のユースケースをサポートできる点で際立っています。CelestiaまたはAvail自体を支えることすらできる:理論的には、どちらのネットワークもEigenLayerのAVSになり、彼らのバリデーターセットをEthereumと融合させることができます。それは彼らが独自のトークンとコミュニティを持っているため、可能性は低いですが、EigenLayerが単一のサービスではなく、プラットフォームであることを示しています。我々は、CelestiaとAvailがEigenLayerのプレイブックから何かを採用するのを見るかもしれません:例えば、将来において、Celestiaが複数のCelestiaインスタンスの間で$TIAの再ステーキングを許可したり、他のチェーンが自身のバリデーターセットを借りることを許可するかもしれません。それはすでにコンセンサスと実行を分けています;Celestiaと他のゾーン(IBCまたは類似のプロトコルを通じて)の間での共有セキュリティの概念を追加することが可能です。
互換性とブリッジ:これら三つのソリューション全てがブロックチェーンの相互作用をスムーズにすることを目指しています。AvailのNexusはAvail上のロールアップを接続します。Celestiaは、他のエコシステムと接続するためにIBCや外部ブリッジ(Hyperlaneのような)に依存しています。EigenLayerは、クロスチェーンのオラクルやブリッジのネットワークを支えることができます。ユーザーはどのチェーンでアプリが動作するかを気にせず、簡単に資産やデータを移動でき、結果を信頼できることを気にします。これらの革新は、例えば、Celestiaにデータを保存し、Ethereumに証明を投稿(EigenLayer経由かもしれません)し、AvailのNexusブリッジを使用して別のロールアップとネイティブに資産をスワップできるアプリケーション固有のロールアップを使用するような、ユーザー向けの世界に向かっています。それは裏で複雑に見えますが、正しく行われるならば複雑さは抽象化され、ユーザーはただ単に迅速で安価なトランザクションと統一されたマルチチェーンウォレットを体験します。
歴史的背景と展望:どのようにしてここにたどり着いたのかを考えてみる価値があります。2010年代後半、スケーリングはオンチェーンシャーディング(Ethereum 2.0の元の計画、後に進化)とマルチチェーンネットワーク、Polkadot(2020年にローンチ)とCosmos(2019年にIBCと共に2021年)について関心が向けられていました。Polkadotはパラチェーン間の共有セキュリティのアイデアを紹介しました;Cosmosはシームレスな互換性(IBC)を紹介しましたが、セキュリティは各チェーンに委ねられました。今日のモジュラーアプローチは、これらのアイデアの統合と見なすことができます:CelestiaとAvailは多くのチェーンに使用される*共有セキュリティ層(データ/コンセンサス用に)*を提供します(多少Polkadotのリレーチェーンに似ていますが、状態の実行なしで厳密な結合もなし)、プロ토コルとしてのEigenLayerとNexusはクロスチェーンコミュニケーションを強調(Cosmosのブリッジング精神に似ています)しています。興味深いことに、Ethereum自体はロールアップ中心のロードマップに転換し、うまくいけば自らをロールアップのための和解とデータ層として位置づけています。2023年のProto-danksharding(EIP-4844)はその第一歩であり、ロールアップのための安価なブロブスペースを追加しました。将来のフルDankshardingにより、Ethereumは大容量のデータ可用性層にもなるでしょう。これはEthereumのL1自体がよりモジュラーになっていることを意味し(コンセンサスとデータに焦点を当て、実行はL2に任せる)、EthereumのロードマップとCelestia/Availのようなプロジェクトの間の哲学的な整合性は、モジュラー設計が広範に将来の道として見られていることを示唆します。
ただし、独立したレイヤーの存在は、一部のガバナンスとインセンティブに関する問題を引き起こします。行動の多くがこれらのレイヤーに移る場合、価値と手数料はどのように分配されるのでしょうか?例えば、Celestiaのトークンはそれを使用するすべてのロールアップから手数料を得るのでしょうか?EigenLayer AVSにセキュリティを提供して稼ぐEthereumの価値はどうでしょうか?おそらく、複数のレイヤーにまたがるMEV(Miner/Maximal Extractable Value)市場が出現するかもしれません – 例として、Celestiaのブロックプロデューサーがロールアップトランザクションの構造を決定するためのMEVオークションを行う,などです。レイヤー間の調整(たとえば、データがCelestia上で最終化された場合にのみロールアップの状態が最終化されることの保証)は、同期の問題や攻撃ベクターを避けて慎重に扱われるべきです。これらは現在も研究と開発が進行中の分野です。
課題と批判
モジュラーアプローチが有望である一方、そのことには独自の課題もあります:
-
複雑性:複数のレイヤー(データ層、決済層、実行層など)の導入は、全体のアーキテクチャをより複雑にします。故障の可能性のあるポイントが増え、同調仮定も増えます。すべての層が正しく会話することを保証するのは簡単ではありません。新しい故障モードが出現する可能性があります – 例えば、データ可用性層がダウンしたり、データが大幅に遅延した場合に何が起こるか?それに依存するロールアップは停止するかもしれません、たとえその実行層が正常でも。
-
レイテンシー:より多くのレイヤーはトランザクションのレイテンシーを追加する可能性があります。Celestiaがデータを最終化するのを待ち、次にEigenLayerのオラクルが何かを更新するのを待たなければならないロールアップは、プロセスを遅くする可能性があります。この問題を最小限に抑えるために設計が最適化されています(Celestiaはほぼ即時の最終化を提供しており、これが役立ちます)。
-
経済的整合性:各レイヤーには独自のトークンがあります(CelestiaのTIA、Availのおそらくそのトークン、EigenLayerはETHを使用するがガバナンス/報酬のためにEIGENトークンも持っています)。これらの間のインセンティブを整えるのは難しいです。例えば、Celestiaのトークン保有者が手数料を高く設定することに投票した場合、ロールアップがAvailに逃げることになるかもしれません?あるいは、EigenLayerのガバナンスとEthereumのコアデベロッパーが許可されるべきサービスについて意見の相違を持つことになるでしょうか?重複するコミュニティが対話を維持する必要があります。
-
セキュリティ仮定:CelestiaとAvailのセキュリティは、それらのバリデーターセットと、最低20%のノードがデータサンプリングのために正直であると仮定される等の仮定に依存します。それらのネットワークが十分な分散化を維持できない、またはサンプリングロジックにバグがある場合、それを使用している人々に対して壊滅的です。EigenLayerのセキュリティはEthereumに依存していますが、それはEthereumの仮定を引き継ぎ、さらに独自の仮定(スマートコントラクトリスク、潜在的な関連するスラッシングが混乱を引き起こす可能性など)を追加します。共有セキュリティはリスクも共有するということです – それが売り文句であり懸念でもあります。広く使用されているレイヤーの1つが妥協された場合、多くのチェーンが影響を受ける可能性があります。例えば、Celestiaのコンセンサスに重大なバグがあると、それに依存する数百のロールアップが影響を受けるかもしれません。とはいえ、分離は故障を封じ込めることもできます:実行層にバグがあれば、エコシステム全体をダウンさせず、ただそのロールアップだけをダウンさせます。
-
規制および社会的側面:より多くの相互接続されたシステムは、大規模なネットワークを思わせるため、規制の精査を引き付ける可能性があります。また、社会的には既得権者からの抵抗があるかもしれません(例:L1プロジェクトである場合、Celestiaを採用することは独自のバリデーターコミュニティを段階的に廃止することを意味するかもしれません)。既存のプロジェクトをモジュラー層に移行するには時間がかかります。
したがって、モジュラークリプトを通じてブロックチェーンを接続するための競争が進行中である一方で、それはスプリントではなくマラソンです。私たちが議論した3つのプロジェクトはすべて、まだ活発な開発中または展開初期段階です。Celestiaはメインネットベータでそのエコシステムが形成中です;Availはメインネットとモジュールのローンチに差し掛かっています;EigenLayerは2024年を通じてEthereumメインネットで段階的にサービスを開放しています。我々は並行実験を目にする可能性が高く、おそらく一部のハイプロファイルな成功例(例えば、Celestiaで独自のチェーンを立ち上げた人気のあるゲームやソーシャルアプリなど)が見られるでしょう。 またはEigenLayerオラクルを使用する主要なDeFiプロトコル)とおそらくいくつかの挫折(これらの新しいシステムのいずれかに初期のバグまたは経済的なエクスプロイトが発生するかもしれません)。
結論: モジュラーで相互接続されたブロックチェーンエコシステムに向けて
Celestia、Avail、そしてEigenLayerの登場は、ブロックチェーン設計におけるパラダイムシフトを示しています。これまでのように、すべてを統治する一つの巨大なチェーンを構築するのではなく、仮想通貨コミュニティは階層をまたいだ専門化と協力を受け入れています。このモジュール型ビジョンは、無数の実行シャードに広がる毎秒数百万トランザクションという前例のないスケーラビリティを約束しており、その間に共有検証およびサンプリング技術を通じてセキュリティを保持または向上させることができます。また、より大きなイノベーションの自由を約束します。開発者は、コンポーネントを組み合わせて(ここからセキュリティ、そこからデータ、好みの実行)アプリケーションニーズに合わせたカスタムプラットフォームを作成できます。
今後数年間で、新たなブロックチェーンの proliferare(普及)が予想されます。それらは孤立せず、基盤層やサービスのタペストリーに接続されます。DeFi交換はあるデータネットワーク上でのロールアップとして運営され、ゲームユニバースはEthereum再ステーカーによって保護された独自のチェーン上に存在するかもしれません。そして、それらは標準化されたブリッジやハブを介して相互運用できます。ユーザーは自分がどのチェーンにいるかを認識しないかもしれません。インターネットアプリのユーザーがどのデータセンターにパケットが到達したかを知らないのと同じように、彼らは単に基盤となるモジュラーインフラがその役割を果たしていることを信頼するでしょう。
重要なのは、このモジュラーアプローチがゼロサムでないことです。Celestia、Avail、EigenLayerはそれぞれがわずかに異なる側面に対処しており、彼らはニッチに焦点を合わせつつ端で協力することで繁栄するかもしれません。たとえば、EigenLayer提供のオラクルを使用するCelestiaロールアップや、Ethereumで重要な証拠を解決するAvailアプチェーンを想像できます。最終目標は、価値と情報がより自由かつ安全に流れる、よりつながったブロックチェーンの世界です。
解決すべき課題もあります。プロジェクトは長期にわたりそのセキュリティと信頼性を証明しなければなりません。経済的には理に適っている必要があります。インフラストラクチャの二層または三層に対する支払いは、ユーザーにとって手頃な価格となるのでしょうか?初期の兆候は好ましいです。専門化は効率向上をもたらすことができるからです(e.g., Celestiaの高スループットはデータ1バイトあたりのコストを下げる可能性があります)。また、開発者がこのモジュール型モデルでアプリを設計するための学習曲線がありますが、OP Stack(Optimismから)やCosmos SDKのようなフレームワークは、それぞれ異なるデータ可用性バックエンドや決済層をプラグインすることを既に進化し始めています。ツールと標準化(たとえば、Ethereum内でCelestiaデータの可用性を検証する方法、EigenLayer上のスラッシング条件を標準化する方法など)が成熟する必要があります。
2025年には、レースが進行中です。Celestiaのチームは「ダイヤルアップからブロードバンドへのブロックスペースを取った」と主張し、現在「光ファイバー」を目指しています。Availの創設者は、異なるロールアップの「統一要因」であることを想像しています。EigenLayerのクリエイターは、Ethereumのセキュリティが再利用可能なリソースとなり「100倍のイノベーション」を予見しています。これはブロックチェーンインフラのエキサイティングな時期です。これらの野心的なプロジェクトはもはやホワイトペーパーだけでなく、実際の価値を保護するライブネットワークとなっています。仮想通貨コミュニティとその広い世界にとって、モジュール型ブロックチェーンは、非中央集権性や相互運用性を妥協せずに、技術が何十億ものユーザーに対応する準備が整ったことを意味するかもしれません。
このレースのフィニッシュライン – 完全につながったモジュラークリプトエコシステム – はまだ先にあります。しかし、Celestia、Avail、EigenLayerが限界を押し広げることで、私たちは、ブロックチェーンのインターネットを目指して着実に歩みを進めています。これは、ウェブと同じくらい柔軟で相互につながったものでありながら、ブロックチェーンが約束する信頼性とセキュリティを備えています。最終的に、このレースの勝者となるのは、より速く、より安価で、シームレスに相互接続されたブロックチェーン体験を享受する可能性のあるユーザーや開発者であるでしょう。この業界を始めた多くの理想を最初に果たすことになります。